
後ほど詳しく解説しますが、危険物乙4の合格点・合格ライン(合格基準)は試験科目(危険物に関する法令・基礎的な物理学及び基礎的な化学・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法)ごとの正答率がそれぞれ60%以上であることです。
本記事では日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の合格点・合格ライン(合格基準)について、出題される問題例とともに詳しく解説していきます。
危険物乙4を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
目次
危険物乙4の合格点・合格ライン・合格基準は?
前提として、危険物乙4では以下の3分野から問題が出題されます。試験時間は2時間です。
※「危険物乙4の試験時間は2時間で問題数は35問!試験は何時から開始?途中退出も可能!」もぜひ合わせてご覧ください。
| 分野 | 問題数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 15問 |
| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 10問 |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 |
危険物乙4の合格点・合格ライン(合格基準)は各分野の正答率が60%以上であることです。
つまり、危険物乙4の合格するには、
- 危険物に関する法令:15×60%=9[問]以上の正解
- 基礎的な物理学及び基礎的な化学:10×60%=6[問]以上の正解
- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法:10×60%=6[問]以上の正解
を叩き出す必要があります。
1分野で100%の正答率(=満点)を取れたとしても、他の1分野の正答率が60%未満だと不合格になってしまうのでご注意ください。
合格・不合格のケース例は以下の通りです。
<合格の例>
| 分野 | 正解数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 9問 |
| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 7問 |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 8問 |
<不合格の例>
| 分野 | 正解数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 12問 |
| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 6問 |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 5問 |
※「危険物に関する法令」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学」は合格基準を満たしていますが、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」は合格基準を満たしていないので、不合格となります。
🔽 合格ラインを余裕で突破! 🔽
危険物乙4の合格率は?
令和元年〜令和5年における危険物乙4の合格率は以下のように推移しているため、危険物乙4の合格率は30%〜40%弱と言えます。
| 年度 | 受験者数[人] | 合格者数[人] | 合格率[%] |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 223,797 | 71,670 | 32.0 |
| 令和4年 | 223,009 | 70,211 | 31.5 |
| 令和3年 | 234,481 | 84,564 | 36.1 |
| 令和2年 | 200,876 | 77,466 | 38.6 |
| 令和元年 | 221,867 | 85,669 | 38.6 |
合格率=30%〜40%弱と聞くと、危険物乙4は難しい試験なのでは?と思う人もいるでしょうが、決してそんなことはありません。
※「危険物乙4の合格率推移!難しくなった?難易度は?難しいから諦める人も?」もぜひ参考にしてください。
危険物乙4の合格に必要な勉強時間は40〜60時間程度と言われています。
1日2時間の勉強を行う場合、単純計算すると20〜30日(=1ヶ月)での合格が可能です。
※「危険物乙4の勉強時間は40~60時間と言われてます!10時間の勉強時間で受かる方法とは?」もぜひ参考にしてください。
となると、出題される問題が難しいのでは?と思う人もいるでしょうが、そんなことはありません。
危険物乙4では応用問題が出題されることはなく、出題される問題はすべて危険物乙4の参考書に掲載されている基礎的な内容です。
なので、危険物乙4は参考書の内容がしっかりと頭に入っていれば確実に合格することができます。
※「危険物乙4のおすすめテキスト・参考書・問題集ランキング2025!人気なのはどれ?」もぜひ合わせてご覧ください。
危険物乙4以外の合格率は?危険物乙4の合格率はなぜ低い?
危険物取扱者試験には甲種・乙種・丙種がありますが、乙種はさらに1類〜6類に分かれています。
乙種1類〜6類の合格率(令和元年〜令和5年)を比較すると、以下のようになります。
| 年度 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 70.0% | 66.8% | 69.2% | 32.0% | 68.4% | 69.2% |
| 令和4年 | 69.4% | 68.9% | 71.1% | 31.5% | 71.0% | 70.0% |
| 令和3年 | 70.5% | 72.3% | 71.0% | 36.1% | 71.0% | 70.7% |
| 令和2年 | 71.5% | 70.8% | 70.8% | 38.6% | 71.2% | 68.5% |
| 令和元年 | 67.9% | 68.5% | 68.2% | 38.6% | 68.7% | 67.0% |
以上の表を見ると、危険物乙4は他の類と比較して合格率が低いことがわかります。
その理由は主に以下の2つです。
- 受験者数が圧倒的に多い
- 他の類に比べて受験目的が多様
それぞれの詳細は以下です。
受験者数が圧倒的に多い
以下の表は令和元年〜令和5年における乙種1類〜6類の受験者数ですが、危険物乙4の受験者数は他の類と比較して圧倒的に多いことがわかります。
| 年度 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 8,737人 | 8,951人 | 10,763人 | 223,797人 | 11,027人 | 10,635人 |
| 令和4年 | 9,498人 | 9,579人 | 11,555人 | 223,009人 | 11,930人 | 11,739人 |
| 令和3年 | 11,168人 | 10,385人 | 13,056人 | 234,481人 | 12,977人 | 13,370人 |
| 令和2年 | 9,190人 | 8,777人 | 10,612人 | 200,876人 | 10,393人 | 11,041人 |
| 令和元年 | 11,465人 | 11,114人 | 12,535人 | 221,867人 | 12,862人 | 12,573人 |
危険物乙4はガソリンスタンドの従業員や消防関連の職種など多くの業界で求められるため、受験者数が他の類と比べて桁違いに多くなっています。
※「危険物乙4で何ができる?できること11個まとめ!」もぜひ参考にしてください。
その結果、資格試験に不慣れな受験者も多くなり、他の類よりも合格率が低くなっています。
他の類に比べて受験目的が多様
乙種1類〜3類、5類〜6類は主に化学系の専門職に就く人が受験することが多いため、受験者のレベルが比較的高い傾向にあります。
一方で、危険物乙4はガソリンスタンドの従業員や消防関係者・高校生・一般の社会人など、幅広い層が受験するため、受験者の学習レベルにバラつきがあり、合格率が低くなりやすい傾向にあります。
※「危険物乙4がガソリンスタンドで重宝される理由と具体的な業務内容・将来性を徹底解説」もぜひ合わせてご覧ください。
🔽 合格ラインを余裕で突破! 🔽
危険物乙4の問題例
本パートでは、危険物乙4の問題例を分野別にご紹介していきます。
危険物乙4の難易度を把握するためにも、ぜひ解いてみてください。
【危険物に関する法令の問題例】
ガソリン1,000L、軽油1,000L、重油1,000L、メチルアルコール1,000Lを、屋内貯蔵所に貯蔵する場合の指定数量の倍数として、正しいものを1つ選びなさい。
- 5倍
- 7倍
- 9倍
- 11倍
- 13倍
【解答&解説】
正解は3・・・(答)です。
それぞれの指定数量はガソリン200L、軽油1,000L、重油2,000L、メチルアルコール400Lです。
よって、倍数は以下のようになります。
- ガソリン:1,000L÷200L=5
- 軽油:1,000L÷1,000L=1
- 重油:1,000L÷2,000L=0.5
- メチルアルコール:1,000L÷400L=2.5
以上を合計すると9倍になります。
※指定数量について詳しく学びたい人は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。
【基礎的な物理学及び基礎的な化学の問題例】
湿度に関する記述で、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
- 一般に用いられる湿度の表し方は、相対湿度である。
- 相対湿度の低いときは、火災の危険性が大きい。
- 過去の相対湿度を考慮に入れた湿度を実効湿度という。
- 相対湿度が高ければ高いほど、火災の危険性は小さい。
- 当日の相対湿度が高ければ、火災の発生、延焼危険は、実効湿度とは無関係である。
【解答&解説】
正解は5・・・(答)です。
火災の発生や延焼危険には、実効湿度が大きく関係しています。
また、物体が過去に吸収し保持している湿度も考慮に入っています。
※「危険物乙4の物理化学は難しい?過去問や覚え方・ポイントや計算問題は?」もぜひ合わせてご覧ください。
【危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法の問題例】
第4類の危険物の火災予防における換気の必要性の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 静電気防止のため。
- 自然発火防止のため。
- 燃焼範囲の下限界よりも低くするため。
- 可燃性蒸気を撹はんするため。
- 湿度を一定に保つため。
【解答&解説】
正解は3・・・(答)です。
第4類危険物の蒸気は比重が1より大きいため、ほとんどが低所に滞留する性質があります。
※「危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせで紹介!性質の問題例は?」もぜひ合わせてご覧ください。
そのため、引火等の危険を避けるには換気と蒸気の排出によって燃焼範囲の下限界より低くします。
危険物乙4の合格点・合格ライン・合格基準を超えるポイント3つ
危険物乙4の合格点・合格ライン(合格基準)を超えるポイントは以下の3つです。
- 自分に合った参考書を購入する
- 危険物乙4の頻出分野を重点的に学習する
- 問題演習をしっかり行う
それぞれの詳細は以下です。
1:自分に合った参考書を購入する
現在は本屋やAmzonなどで危険物乙4の参考書が数多く販売されています。
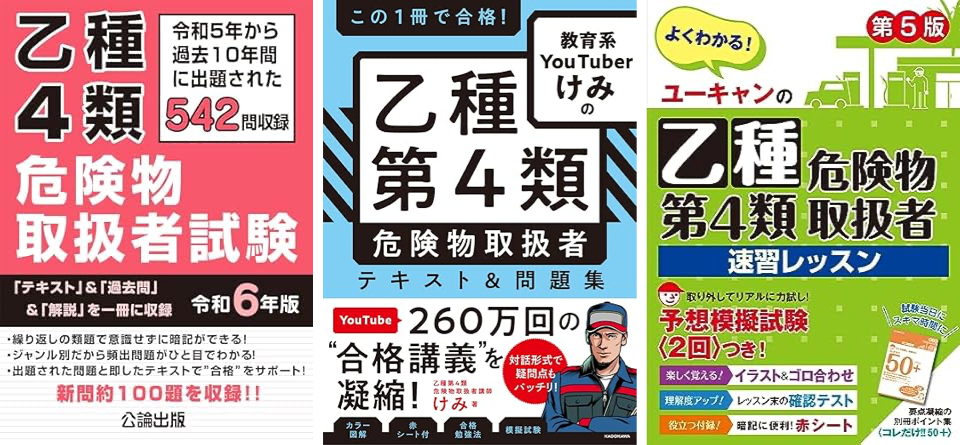
中には、イラストや図解があまり使用されておらず、文字量がかなり多い参考書もあります。
文字が多くても平気な人はそのような参考書を購入して学習を進めても問題ないですが、文字を読むのが苦手な人はイラストや図解が豊富に使用されている参考書を購入すると良いでしょう。
危険物乙4に限らずですが、参考書は実際に中身を見て、自分が勉強を続けられそうな内容・構成になっているかを確認してから購入するのがおすすめです。
なので、危険物乙4の参考書を購入する人はAmazonなどのネットで購入するのではなく、実際に本屋にまで足を運び、立ち読みをした上で購入しましょう。
2:危険物乙4の頻出分野を重点的に学習する
危険物乙4の試験範囲はかなり広いので、あらゆる分野の問題がある程度均等に出題されると思っている受験者もいますが、そんなことはありません。
危険物乙4には以下の通り頻出問題が存在します。
※「危険物乙4でよく出る問題・頻出問題52選!丁寧な解答・解説付き」もぜひ合わせてご覧ください。
| 分野 | 頻出問題 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 第1類〜第6類の性質、指定数量、運搬の基準、貯蔵・取扱いの基準 |
| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 静電気、燃焼 |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 特殊引火物・アルコール類・ガソリン・灯油・軽油に関する問題 |
なので、危険物乙4を受験予定の人は上記の頻出問題を特に重点的に学習することをおすすめします。
ちなみにですが、その中でも静電気に関する問題は特に出題頻度が高いです。
静電気に関する問題の例題は以下です。
【例題】
静電気について、次のうち誤っているものはどれか。
- 静電気の放電火花は可燃性蒸気の点火源になることはない。
- 電気の不導体に帯電しやすい。
- 一般に合成繊維製品は、綿製品よりも帯電しやすい。
- 湿度が低い方が帯電しやすい。
- 帯電防止策として、接地する方法がある。
【解答&解説】
正解は1・・・(答)です。
「点火源になることはない」が誤りです。静電気の放電火花は可燃性蒸気の点火源になり、静電気火災が発生する危険性があります。
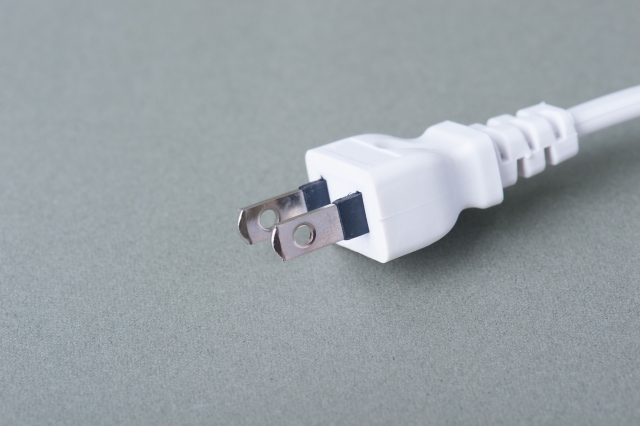
危険物乙4に限らずですが、資格試験を受験する場合は頻出分野がどこかを必ず把握した上で学習を進めるようにしましょう。
3:問題演習をしっかり行う
危険物乙4では過去問の類似問題がたくさん出題されるのが特徴です。
例えば、以下2つの問題はともに危険物乙4の過去問ですが、内容がかなり似ていることがわかります。
※「危険物乙4の過去問・試験問題100問が無料!解説付き!PDFも配布!」もぜひ合わせてご覧ください。
【問題1】
危険物保安監督者を選任しなくてもよい製造所等はどれか。
- 製造所
- 屋外タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 給油取扱所
- 移送取扱所
【解答&解説】
正解は3・・・(答)です。
危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等は以下の5つのみです。
- 製造所
- 屋外タンク貯蔵所
- 給油取扱所
- 移送取扱所
- 一般取扱所(容器の詰替などを除く)
移動タンク貯蔵所とは一般にタンクローリーのことをいい、危険物保安監督者の選任は不要です。
【問題2】
法令上、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等に該当するものとして、正しいものはどれか。
- 指定数量の倍数が30の屋外貯蔵所
- 指定数量の倍数が30を超える移動タンク貯蔵所
- 指定数量の倍数が30を超える危険物を容器に詰め替える一般取扱所
- 指定数量の倍数が30を超える引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱う販売取扱所
- 指定数量の倍数が30を超える引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する屋内タンク貯蔵所
【解答&解説】
正解は5・・・(答)です。
※「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」もぜひ合わせてご覧ください。

問題1の解答&解説の通り、危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等5つには屋内タンク貯蔵所が含まれます。
以上より、危険物乙4の過去問に近い問題が掲載された問題集をひたすら解いて暗記していくことは、非常に効率の良い勉強法と言えます。
参考書で危険物乙4の内容がある程度頭に入った後は、問題集でしっかりと問題演習を積むようにしてください。
🔽 合格ラインを余裕で突破! 🔽
今回は危険物乙4の合格点・合格ライン・合格基準について解説しました。
危険物乙4は決して難しい試験ではありません。
事前にしっかりと勉強・対策をすれば間違いなく合格可能です。


