
今では、インターネット上に危険物乙4に関するブログや情報サイトが数多くあります。
特にブログの中には、受験体験談や試験会場の雰囲気などを詳しく紹介しているものもあり、受験を予定している人にとって非常に参考になります。
というわけで今回は、危険物乙4のブログ・情報サイトをまとめてみました。
どのブログ・サイトも役立つ情報が満載なので、危険物乙4を受験予定の人はぜひ参考にしてください。
目次
- 危険物乙4のブログ・情報サイトまとめ59選
- 1:電気の資格独学ブログ
- 2:ふじものブログ
- 3:くじらいどブログ
- 4:イトケンブログ
- 5:又二郎の大食い&デカ盛り&ラーメン日記
- 6:ミチくさ50のブログ
- 7:うらひろ乙4試験対策ブログ
- 8:マイログ
- 9:乙四ドットコム
- 10:Waka BLOG
- 11:SAT株式会社のブログ
- 12:さんぶんのいち
- 13:思い立ったらブログ書こう。
- 14:そんさんブログ
- 15:電気設備屋さんのおすすめ資格ブログ
- 16:独学のオキテ
- 17:平太の雑談ブログ
- 18:オツヨンパパブログ
- 19:ままにブログ
- 20:資格の学校TACのブログ
- 21:やさすけのブログ
- 22:関西B級グルメブログ
- 23:大分県中津市橋口電工スタッフブログ
- 24:黒子ビルメンの日々
- 25:教科書に載っていない現場目線の国際物流ブログ
- 26:たけの資産・資格ブログ
- 27:30代のじゆうちょう
- 28:資格独学取得ブログ〜なめこの資格体験記〜
- 29:kiki blog
- 30:のぼゆエンジニアリング
- 31:Mr.テレビっ子!
- 32:資格と独学のブログ
- 33:CookingPapa.work
- 34:コレハジ
- 35:タクテク2
- 36:Chem-Station
- 37:Recommend Task
- 38:趣味は資格です
- 39:脱線おじさんの独学記
- 40:学習雑記帳
- 41:可能性は無限大
- 42:fukuzublog
- 43:強欲な青木&消防設備士オフィシャルサイト
- 44:夢みる資格研究所 乙4支所
- 45:ASATO BLOG
- 46:電気エンジニアのツボ
- 47:jjpapa.blog
- 48:DODO BLOG
- 49:続・理系院卒から目指す保育士試験合格への道
- 50:マイカ@たつおブログ
- 51:Anon Re:port
- 52:きんげの資格部屋
- 53:HOSIGO
- 54:火消しの雑記帳
- 55:30代からのビルメン転職成功ブログ
- 56:PikoPikoBlog
- 57:オクラビット
- 58:いいことあるよ!
- 59:技術資格オープンラボ
危険物乙4のブログ・情報サイトまとめ59選
では早速、危険物乙4のブログ・情報サイトを一気にご紹介していきます。
それぞれの特徴や得られる情報もご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
1:電気の資格独学ブログ
最初にご紹介するのは「電気の資格独学ブログ」です。
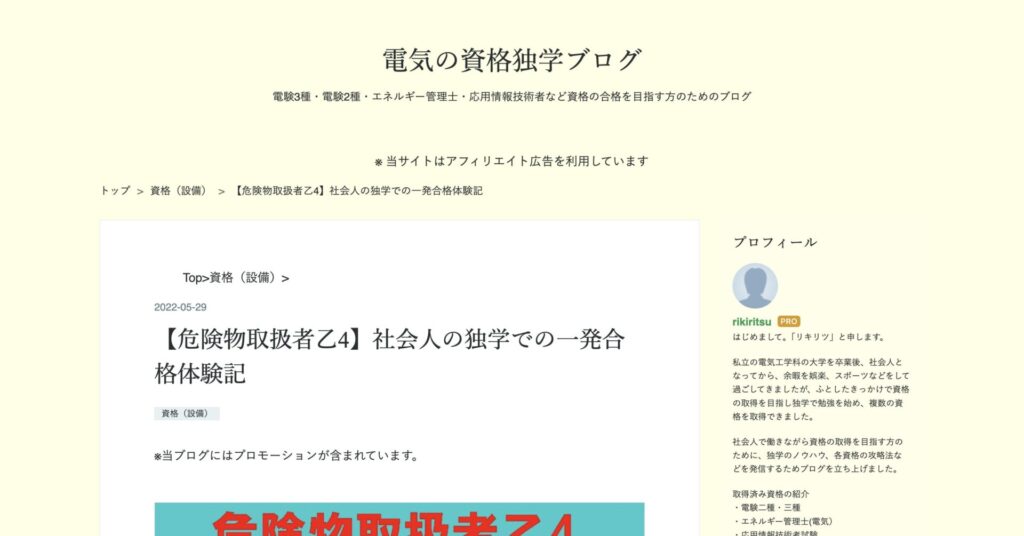
「【危険物取扱者乙4】社会人の独学での一発合格体験記」という記事があり、筆者が社会人の立場から 危険物乙4を独学で一発合格した実践状況が非常にリアルに綴られています。
使用した教材や勉強法、スケジュールの組み方が丁寧に整理されており、仕事の合間を縫ってどのように学習時間を確保したのかがよくわかります。
また、「もっと効率的にできた点」「ここでつまずいた」といった振り返りも率直に書かれており、単なる成功談ではなく、再現性のある現実的な学習プロセスとして参考にできる構成になっています。
全体を通して、社会人が限られた時間の中で資格試験に挑戦する際のリアルな視点が貫かれており、これから危険物乙4を受験しようとする人にとって、実践的な成功の地図となる内容です。
2:ふじものブログ
続いてご紹介するのは「ふじものブログ」です。

筆者が実際に危険物乙4に挑戦した体験を詳細に綴った記事があり、資格取得までの全プロセスが具体的に記録されているのが特徴です。
試験の申し込みから合格通知、免状交付までの流れが時系列で解説されており、「試験手数料4,600円、払込手数料230円」といった実際にかかる費用や、「受験票はコンビニのコピー機でプリントアウトして写真を貼り付ける」といった準備の具体的なステップが丁寧に説明されています。
さらに、学習方法についても「色刷りの問題集は苦手なのでシンプルなものを選んだ」「3~4回繰り返して読み解いた」といった実践的なアプローチが共有されており、化学が苦手な筆者がどのように基本的な内容を習得したかという、初心者目線の学習戦略が参考になります。
3:くじらいどブログ
次にご紹介するのは「くじらいどブログ」です。筆者が夜間セルフガソリンスタンド監視のアルバイトを目指して危険物取扱者乙種4類に合格した体験を綴ったブログで、実務的な動機と資格取得後のキャリアパスまでを網羅しているのが特徴です。
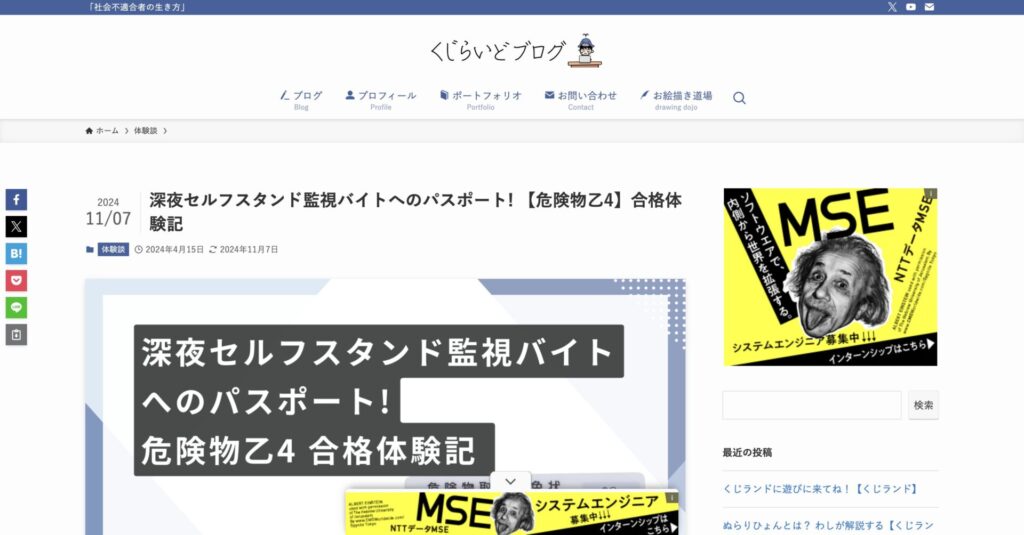
試験の基本情報が表で整理されており分かりやすく、学習教材の紹介が特に充実しています。
「ピンク本」「赤本」といった定番参考書の特徴や、YouTube動画教材といった複数の学習方法が具体的に紹介されており、自分に合った学習スタイルを選べます。
特に注目すべきは、危険物乙4取得後のキャリアパスの提示です。他の乙種資格への科目免除制度、ビルメン業界へのステップアップ、夜間セルフガソリンスタンド監視バイトでの資格活用といった具体的な進路例が複数紹介されており、資格取得がゴールではなく、その先の活用方法まで視野に入れた情報が得られます。
資格取得後のキャリア形成を考えている受験者にとって、特に役立つブログになっています。
4:イトケンブログ
次にご紹介するのは「イトケンブログ」です。筆者が危険物乙4の試験に向けて、学習の途上を綴った個人ブログで、受験直前の正直な学習状況と課題が率直に共有されているのが特徴です。
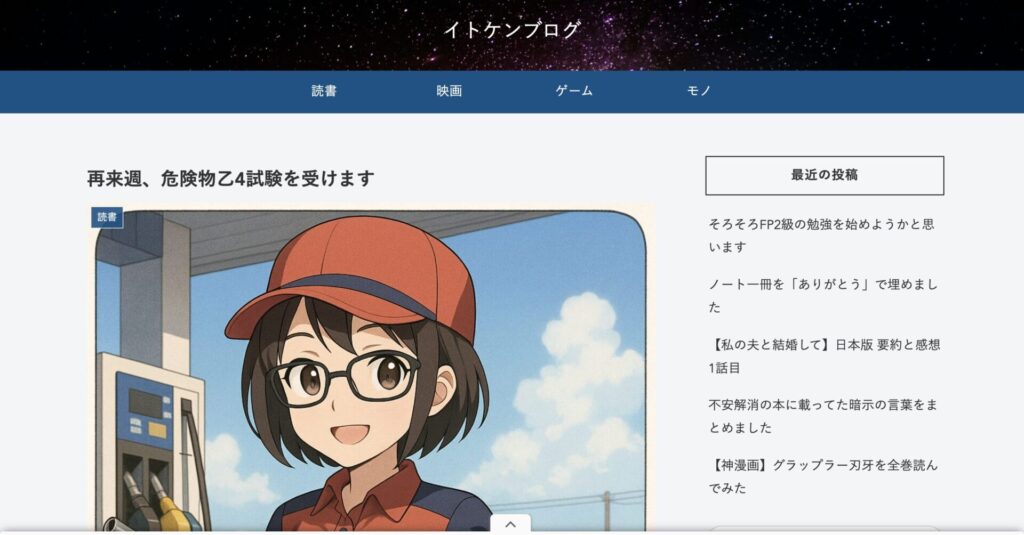
このブログの大きな特徴は、模擬試験での失敗から各科目の難易度を冷静に分析している点です。
全体では71.4%の正答率でも「危険物に関する法令」で6割未満に落ち込んで不合格となった経験から、「法令が苦手」という課題を明確に認識し、対策の方向性を示しています。
一方で、「基礎的な物理・化学」と「危険物の性質」は得意だという自己評価も記載されており、科目ごとの得意・不得意が具体的に浮き彫りになっています。
学習教材としてはユーキャンのテキストとスマホアプリを活用し、「スマホアプリの〇✕問題に慣れるだけでも試験の5択問題を解く力が身につく」というスキマ時間活用のヒントも提供されています。
5:又二郎の大食い&デカ盛り&ラーメン日記
次にご紹介するのは「又二郎の大食い&デカ盛り&ラーメン日記」です。
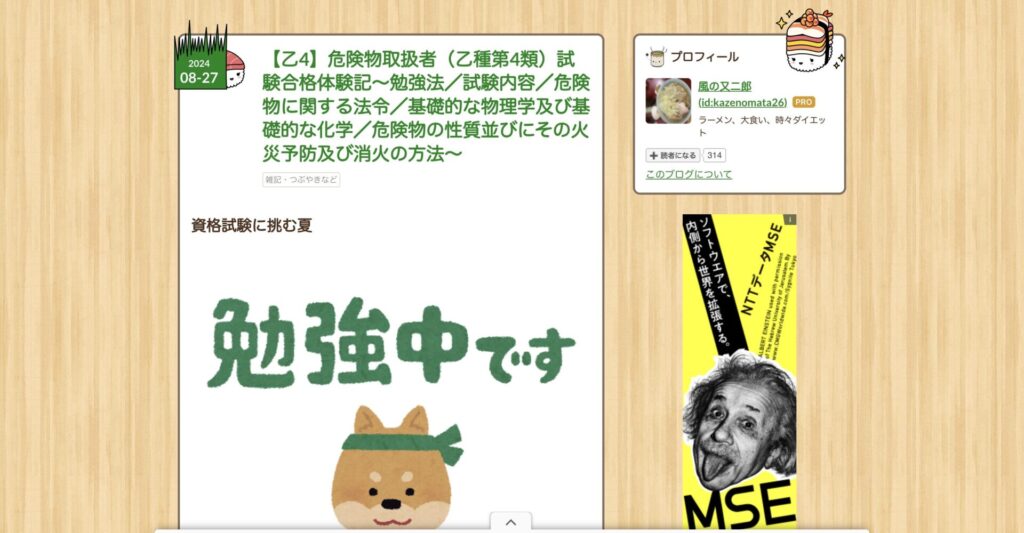
このブログの大きな特徴は、効果的な学習順序を明確に提示している点です。
通常は法令から始まることが多いのに対し、筆者は「物理・化学」→「危険物の性質」→「法令」という順序を推奨しており、その理由を「引火点など基礎科目の内容が全体の基本に通じているから」と丁寧に説明しています。
物理・化学が合否の分かれ目となるため、特に文系受験者にとって参考になる学習戦略です。
テキスト選びのポイント(「絵やイラストが豊富でイメージしやすいテキストを選ぶ」)や、消防試験研究センターの過去問に加えて「過去問.com」といったサイト活用、試験当日の注意点(マークシート方式での慎重さ、問題文の読み込み)といった実務的な情報も充実しています。
6:ミチくさ50のブログ
次にご紹介するのは「ミチくさ50のブログ」です。50代未経験の筆者が危険物乙4に合格した体験を綴ったブログで、中高年からの資格取得という現実的なチャレンジが等身大の視点で記されているのが特徴です。

使用した参考書の「10日で受かる!」という理想計画と実際のボリュームのギャップから「30日でなんとかする!」へ現実対応した学習戦略が、ユーモアを交えながら詳しく記載されています。
エビングハウスの忘却曲線理論をベースに「1日分の学習内容を最低6回復習する」という確実な定着方法や、アプリでリマインダーを組むといった実践的な工夫が紹介されています。
一方で、「復習5本立て興行」や「問題文の読み間違い」といった学習過程での落とし穴も率直に共有されており、過去問の「意地悪さ」に引っかかることの実例が具体的に示されています。
中高年からの資格取得を目指す受験者にとって、年代別の学習アプローチと現実的な課題の両方を学べるブログです。
7:うらひろ乙4試験対策ブログ
次にご紹介するのは「うらひろ乙4試験対策ブログ」です。サイト名から分かる通り、危険物乙4の試験対策に特化したブログです。

危険物乙4試験対策に特化したブログということで、受験に必要な知識や勉強方法、過去問解説、試験対策のコツなど、試験合格に直結した情報が体系的に整理されているのが特徴です。
他の多角的なコンテンツを扱う個人ブログとは異なり、危険物乙4に関心のある受験者が必要とする情報に特化している点が大きな利点となります。
情報を効率よく集めたい、専門的で信頼性の高い対策情報を探している受験者にとって、迷わずにすぐに活用できるブログになっています。
8:マイログ
続いてご紹介するのは「マイログ」です。
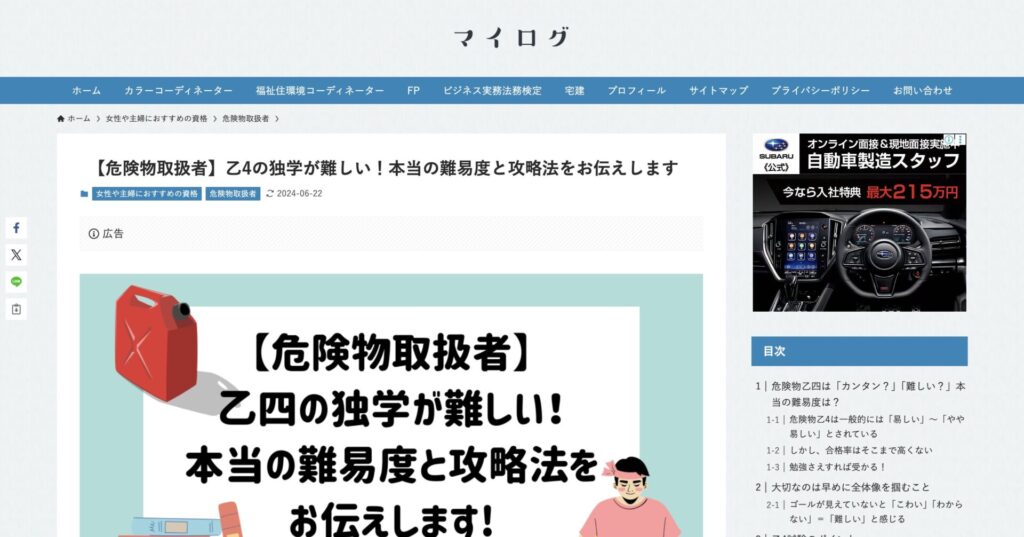
このブログの大きな特徴は、危険物乙4が「簡単」というイメージと「実際の合格率30~40%」というギャップを丁寧に分析している点です。
不合格者の中には勉強に手を付けていない人や一夜漬けで挑んだ人が多いという事実を示しながら、「きちんと勉強することさえできれば必ず合格できる資格」という前向きなメッセージを伝えています。
学習方法として「全体像を早く掴くこと」を重視し、目次を読んでから過去問をチェックするという効率的な学習順序を提示しています。標準的な勉強時間が40~60時間とされる中で、「勉強が難しいと感じている人は30~40時間を目標に」という現実的なアドバイスも含まれており、テキスト選びのコツやスタディングといった通信講座の活用法も紹介されています。
9:乙四ドットコム
次にご紹介するのは「乙四ドットコム」です。危険物乙4の講習会を実施する事業者が運営するブログが用意されており、複数の講習会開催レポートを通じて、実践的かつ現場感のある学習情報が共有されているのが特徴です。

このブログの大きな特徴は、東京・大阪での定期的な講習会の開催実績と、その講習会での具体的な指導内容がレポートとして記載されている点です。
「計算問題は正攻法だけが回答方法ではなく、マークシートの5択を利用して答えを見つけることができる」「難問は捨ててもよいが、視点を変えると簡単に解ける問題もある」といった、試験テクニックが具体的に紹介されています。
また、「危険物乙4と相性の良い資格」といった記事も掲載されており、取得後のキャリアパスについても言及されています。
10:Waka BLOG
次にご紹介するのは「Waka BLOG」です。化学が苦手で高校時代に赤点を経験した筆者が、危険物乙4に一発合格した体験を綴ったブログで、化学トラウマ克服という心理的課題を含めた実体験が特徴です。

受験のきっかけがガソリンスタンドバイト時代の悔いという個人的な動機から始まり、勉強開始時の葛藤、試験当日の不安な心情まで、等身大の感情が丁寧に描かれています。
使用したテキスト(公論出版の過去問集と「10日で受かる」シリーズ)が具体的に紹介されており、試験会場となった中央試験センターの様子も画像付きで詳しく記載されています。
特に注目すべきは、試験結果が予想外に良かった点です。化学が最も不安だった筆者が、物理・化学で100%、性質・消火でも100%という結果を得ており、「化学トラウマを克服できた」というストーリーが、同じく化学に苦手意識を持つ受験者に大きな励みになるブログです。
11:SAT株式会社のブログ
続いてご紹介するのはSAT株式会社のブログです。危険物乙4に約1ヶ月で合格を目指す勉強方法を体系的に解説するブログが用意されており、資格教育の専門業者による実践的で信頼性の高い情報が特徴です。

このブログの大きな特徴は、効率的な学習順序を明確に示している点です。
「物理・化学から勉強する」「危険物の性質は徹底的に暗記」「法令は最後に」という3段階の学習戦略が提示され、各段階での重点項目が詳しく解説されています。
また、「燃焼の3要素」や語呂合わせ「固い人に駅で無視された」といった具体的な暗記テクニックも紹介されており、初心者にとって理解しやすくまとめられています。
さらに、合格率が30~40%と低い背景にある「3つの要因」(受験者が多い、受験資格がない、全科目で60%以上必須)の丁寧な分析や、試験当日の解答テクニック(マークシート記入時に2周以上確認してからまとめる)といった実務的な情報も充実しています。
12:さんぶんのいち
続いてご紹介するのは「さんぶんのいち」です。自宅リフォーム計画のために危険物乙4に合格した筆者の体験を、申込から免状交付までの全プロセスを画像付きで詳しく記載した個人ブログで、実務的かつ細部にわたった情報が特徴です。

電子申請ができる場合・できない場合の条件、複数受験時に書面手続きが必要といった実務的なポイントも示されており、初めて受験する人が迷わないようなガイドが充実しています。
使用教材の詳細な評価(公論出版の過去問、ユーキャンテキスト、「10日で受かる」シリーズ)も記載されており、「テキストを3回読んで過去問を3周」という具体的な学習方法が示されています。
特に注目すべきは、成績が「法令86%、物理・科学100%、性質・消火100%」という結果について、試験中に迷った法令の2問が外れた正確な記録であり、得点と試験当日の実感の一致が記載されている点です。
受験にかかる費用の明細(交通費・宿泊費含む)も列挙されており、試験準備の全体像を把握したい受験者にとって、実用的かつ網羅的なブログです。
13:思い立ったらブログ書こう。
次にご紹介するのは「思い立ったらブログ書こう。」です。アラフィフおやじが危険物乙4に3ヶ月かけて合格した体験を、日程を追いながら詳細に綴ったブログで、中高年からの受験者にとって特に参考になる現実的な学習アプローチが特徴です。
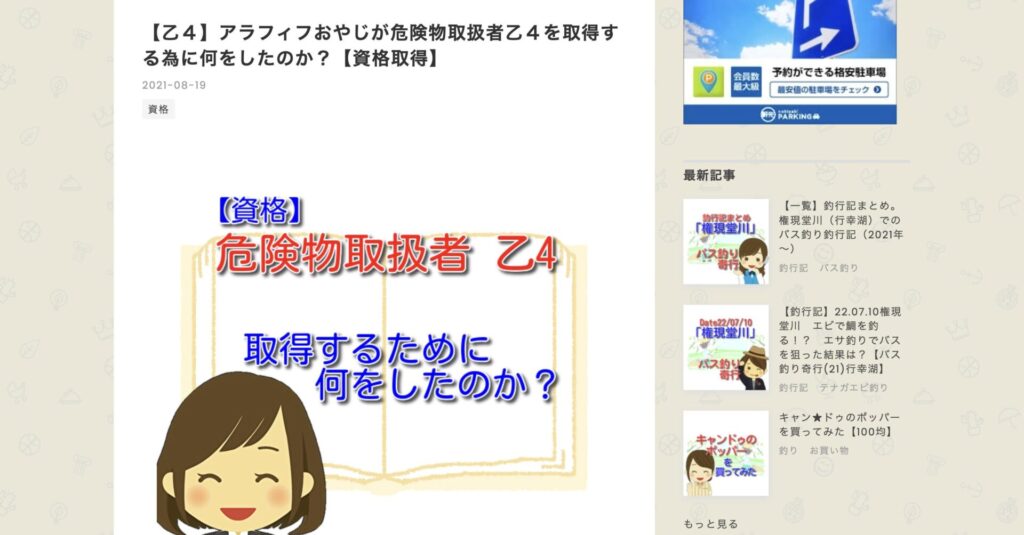
模擬テストで法令90%、物理化学80%、性質消火95%という結果を得た後に、ネット問題集で想定外の問題が出ることに直面し、1週間前に急遽追加学習する状況がリアルに描かれており、試験対策の現実的な課題が伝わってきます。
また、独学による効率的な暗記法として「一覧表の作成」、試験当日の具体的な工夫(△マークで自信がない問題を標識、問題文の重要部分にアンダーライン)、「正しいもの」「誤っているもの」の見落としを防ぐ技法なども紹介されています。
最終的には法令86%、物理化学90%、性質消火90%という成績を得ながら、「最後まで不安だった」という本音も共有されており、中高年の受験者が感じるであろう不安感と、それでも最後まで準備を続けることの重要性が実感として伝わるブログです。
14:そんさんブログ
次にご紹介するのは「そんさんブログ」です。危険物乙4の魅力とデメリットに焦点を当てた記事が用意されており、受験を検討している人が資格取得の価値を判断するために必要な情報が、バランスの取れた視点で整理されています。

この記事では、危険物乙4の「メリット5つ」と「デメリット5つ」が対称的に解説されています。
メリット側では「就職や転職に有利」「安全管理への理解向上」「キャリアの発展」といった職業的価値を示す一方で、デメリット側では「時間と費用の消費」「学習の難易度」「試験合格の不確実さ」「資格の有効期限」といった現実的な課題を率直に提示しており、初心者が受験判断をする際に役立つ情報バランスになっています。
さらに、危険物乙4が活躍できる職業が列挙されており、資格取得後のキャリアイメージが掴みやすくなっています。勉強方法として「本での学習」「YouTubeで学ぶ」「通信講座」の3つのアプローチを紹介し、各種参考書やYouTubeチャンネル、通信講座まで具体的に推奨されており、自分に合った学習方法を選択しやすいブログになっています。
15:電気設備屋さんのおすすめ資格ブログ
「電気設備屋さんのおすすめ資格ブログ」では危険物乙4に特化したカテゴリーが用意されています。
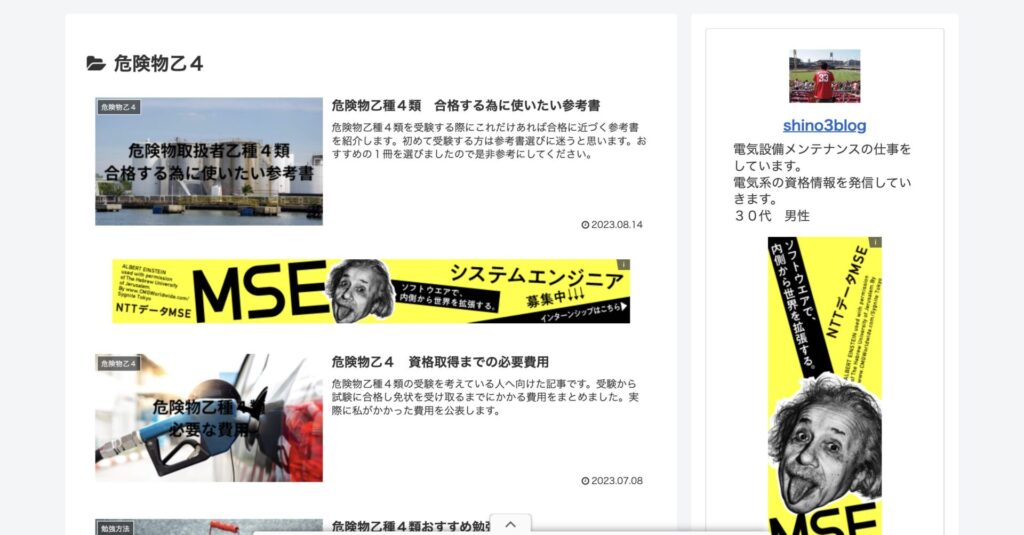
学生時代に危険物乙4を取得した筆者が、「過去10年分の問題を繰り返し解くことが合格への最短ルート」と強調し、難しく考える必要のないシンプルな学習方法を提示しています。
費用面では受験申請から免状取得まで具体的な金額を列挙し、1回の合格で約10,913円の総費用を示しており、受験準備の全体像が把握しやすくなっています。
合格体験記では高校生がガソリンスタンドの時給アップを目指して受験し、その後実務で危険物取扱所の点検業務に活かす事例が紹介されており、学生から社会人まで幅広い受験者にとって実用的なブログです。
16:独学のオキテ
次にご紹介するのは「独学のオキテ」です。文系の筆者が危険物乙4に合格した体験を綴ったブログで、「危険物乙4はカンタン」というネット情報への痛烈な異議申し立てが特徴です。

テキストだけで合格を目指した筆者は、試験本番で「テキストより数倍難しい問題」に直面し、その後本屋で他のテキストを探しても「市販の教材と本試験には結構な差がある」ことに気付きました。
特に「基礎的な物理学及び基礎的な化学(物化)」は文系の鬼門で、試験は「6割が基本問題、4割が応用的・実務的出題」の構成のため、基本6割を100%取らないと不合格のリスクが高まると指摘しています。
難化傾向にある試験の実態と、市販教材では対応できない応用問題の対策の難しさを正直に語っており、「危険物乙4はカンタン」という言説を信じて受験しようとする人にとって、特に文系受験者が知るべき現実的な情報を提供するブログです。
17:平太の雑談ブログ
「平太の雑談ブログ」は危険物取扱者・甲種に合格した筆者が、危険物乙4のおすすめテキストを厳選して紹介するブログで、実際の受験経験に基づいた実用的なテキスト評価が特徴です。

特に注目すべきは、化学が苦手な受験者向けに「鎌田の化学基礎をはじめからていねいに」という高校化学用の参考書も推奨している点です。
筆者は「危険物乙4の試験用テキストで出てくる化学の公式が分からない場合、高校化学の参考書で復習すれば驚くほど理解できる」とアドバイスしており、通信講座のメリットがないことも明言しています。
「一夜漬けで合格できる」という噂を否定し、1~2ヶ月のコツコツ勉強が重要であることを強調する、バランスの取れたブログです。
18:オツヨンパパブログ
「オツヨンパパブログ」は危険物乙4に独学で一発合格した筆者が、実務経験をもとに試験概要から学習ツール選びまでを丁寧に解説するブログです。

最大の特徴は、現場エンジニアとしての視点から「アプリ学習とテキスト学習をどう組み合わせれば最短で合格できるか」を体系的に紹介している点にあります。
特におすすめしているのは、無料で使える学習アプリ「危険物乙4一問一答」と「危険物乙4(おつよん)全問解説」です。それぞれの問題数・使いやすさ・解説の質を比較しながら、スキマ時間で効率よく暗記できる方法を提案しています。
一方で、筆者は「アプリだけでは理解が浅くなる」と警鐘を鳴らし、主要出版社のテキストをレベル別にレビュー。初心者から短期合格を目指す人まで、目的に応じた教材選びをサポートしています。
19:ままにブログ
「ままにブログ」には危険物乙4をわずか3日間の勉強で合格した筆者の体験が掲載されており、超短期合格という一見無謀な挑戦の実現方法が詳しく記録されているのが特徴です。

筆者は法令100%、物化100%、性消90%という高成績を達成しており、3問分からない問題があったにもかかわらずほぼ満点での合格に至った経験が示されています。
合格ノート(実際にはメモ)を公開しており、試験直前に歩きながら確認できるように作られた最後の最後まで覚えられなかった部分がまとめられています。
筆者は「1週間、過去問を3~4周すれば99%受かる」と述べており、合格率30~40%というパーセンテージだけでは試験の難易度を判断してはいけないこと、適切な対策を立てれば確実に受かる試験であることを強調しています。
受験まで時間がない人や、短期集中で合格を目指す人にとって、具体的かつ実用的な参考情報が得られるブログです。
20:資格の学校TACのブログ
資格の学校TACのブログには危険物乙4に関する様々な情報が掲載されています。

中でも「危険物乙4はこうやって攻略する!合格のポイントを伝授」というブログでは、「インプット→アウトプット→インプット…」という繰り返し学習法を基本とし、「テキスト読む→小問題を解く→テキストをもう一度読む→小問題をもう一度解く」という具体的な学習サイクルが示されています。
さらに、テキスト選びではイラスト・多色刷りの重要性、「ロールプレイングで講師を演じてみる」というアウトプット学習法、ガソリンスタンドの構造など日常生活での復習の活用といった、実践的かつ心理学的なアプローチが紹介されています。
実際の試験問題を交えた解説もあり、資格学校による体系的でプロフェッショナルな学習ガイドが得られるコンテンツです。
21:やさすけのブログ
次にご紹介するのは「やさすけのブログ」です。学生時代ほとんど勉強をしてこなかった筆者が、約2ヶ月(1日1時間程度)で危険物乙4に合格した体験を綴ったブログで、勉強が苦手な人向けの実用的かつシンプルな学習方法が特徴です。

このブログの大きな特徴は、「映像(動画)を見て勉強し、過去問を解く」というシンプルな学習方法を提示している点です。
視覚と聴覚に働きかける動画学習が文字だけの学習より2倍記憶に残ると説明し、YouTubeの「優しい乙4対策講座」(5~10分の短編動画)と「電験合格」(最長50分を超える詳しい動画)を紹介しています。
動画視聴と並行して「過去問.com」で過去問を解き、「ぜんせきweb 乙4模擬試験」で5回の無料模擬試験にチャレンジすることで、合格ラインに到達するまでのプロセスが示されています。
22:関西B級グルメブログ
「関西B級グルメブログ」は危険物乙4に独学で合格した筆者が、試験地の下見から試験当日、合格後の免状取得に至るまで、充実したプロセスを時系列で詳しく記載したブログで、実務的かつ心理的なサポート情報が特徴です。

このブログでは、暗記のコツとして「運動しながら単語帳を読む」「夜の22時~2時のゴールデンタイムに勉強」「寝起き直後に前日分を復習」といった、脳科学に基づいた学習方法が提示されています。
また、危険物分類の覚え方や指定数量の計算、保安講習の違い、消火設備の分類など、試験に頻出する細かい法令や知識を、実際に筆者が苦労した個所を含めてリストアップしており、受験者が陥りやすい落とし穴まで示されています。
23:大分県中津市橋口電工スタッフブログ
「大分県中津市橋口電工スタッフブログ」では危険物乙4に1発合格した筆者が、試験当日の心理状態から合格発表後の喜びまでを、等身大の感情を込めて綴ったブログです。

このブログの大きな特徴は、試験当日に筆者が経験した不安が率直に描かれている点です。
暗記に強い法令と性質・消火は順調でしたが、化学では見たことない問題が3問出題され、計算問題の公式を忘れて「終わった、また半年後か」という絶望感さえ感じたにもかかわらず、実は計算問題の「運任せが当たった」ことで合格に至ったという、試験の不確実性と運の要素が描かれています。
学習方法は「2ヶ月間、1日2時間」「『10日で受かる危険物乙4試験』というテキストを隅々まで勉強」「分からないところは先輩に相談」「苦手科目(化学)を重点的に」といったシンプルで実用的なアプローチが示されており、仕事で必要な資格取得という背景も語られています。
24:黒子ビルメンの日々
次にご紹介するのは「黒子ビルメンの日々」です。ビルメン業界にいる筆者が危険物乙4に合格した体験を、簡潔かつ実務的にまとめたブログで、特に20年以上化学から遠ざかった社会人受験者にとって参考になるコンテンツが特徴です。
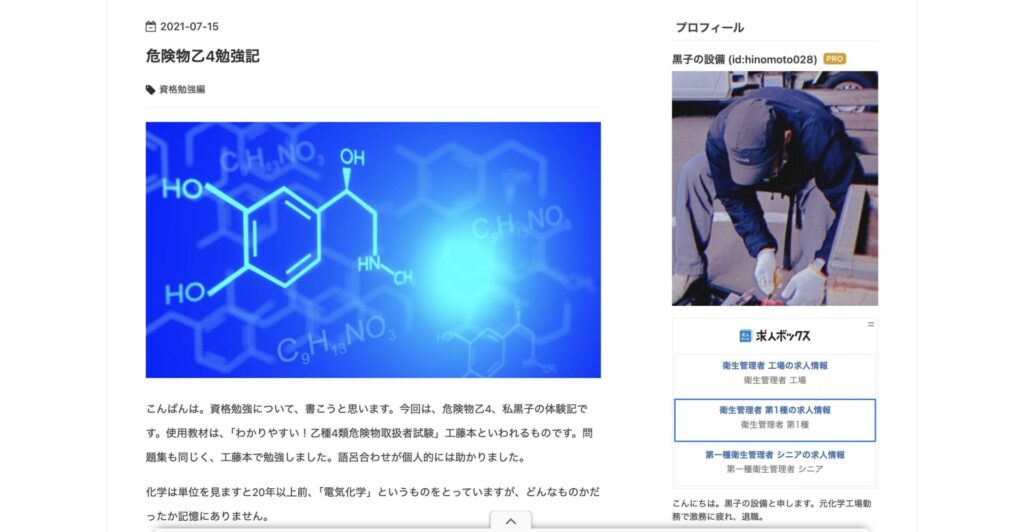
このブログの大きな特徴は、「物理化学」を「鬼門」と位置づけ、高校で物理・化学をそこそこやってきた人しか解けない応用問題は「捨てる」という現実的な割り切りを提示している点です。
法令と性質は「丸暗記」、物理化学は「問題集をやりこんで及第点を狙う」という、限られた時間での効率的な学習戦略が示されており、参考書・問題集2周で約42時間の勉強で合格に至った実績が紹介されています。
25:教科書に載っていない現場目線の国際物流ブログ
「教科書に載っていない現場目線の国際物流ブログ」は国際物流営業の筆者が危険物乙4に合格した体験を綴ったブログで、試験の難易度を甘く見たことへの反省と、実務での活かし方までを詳しく記載しているのが特徴です。

このブログの大きな特徴は、受験の動機が業務に直結している点です。
英文SDS(安全データシート)から消防法の分類ができるようになることで、顧客のニーズに応えたいという実務的な目標が明確に示されており、試験学習が単なる資格取得ではなく、仕事の質向上に繋がることが強調されています。
筆者は試験本番で正直に「物理・化学は勘で5問解いた」「法令と性質でも半分が2択までしか絞れない」という失敗を共有しており、「通関士試験より難しく感じた」「運が良かったの一言に尽きる」という率直な感想を述べています。
反省点として「物理・化学への勉強時間配分が不足」「練習問題の量が圧倒的に少なかった」ことを指摘し、文系受験者向けに「物理・化学に勉強時間を投下すべき」とアドバイスしています。
26:たけの資産・資格ブログ
「たけの資産・資格ブログ」は危険物乙4に独学で一発合格した筆者が、効率的な勉強方法と具体的な学習手順を、実用的かつ詳しく解説したブログで、最小限の費用と時間で合格を目指す受験者にとって特に参考になるコンテンツが特徴です。
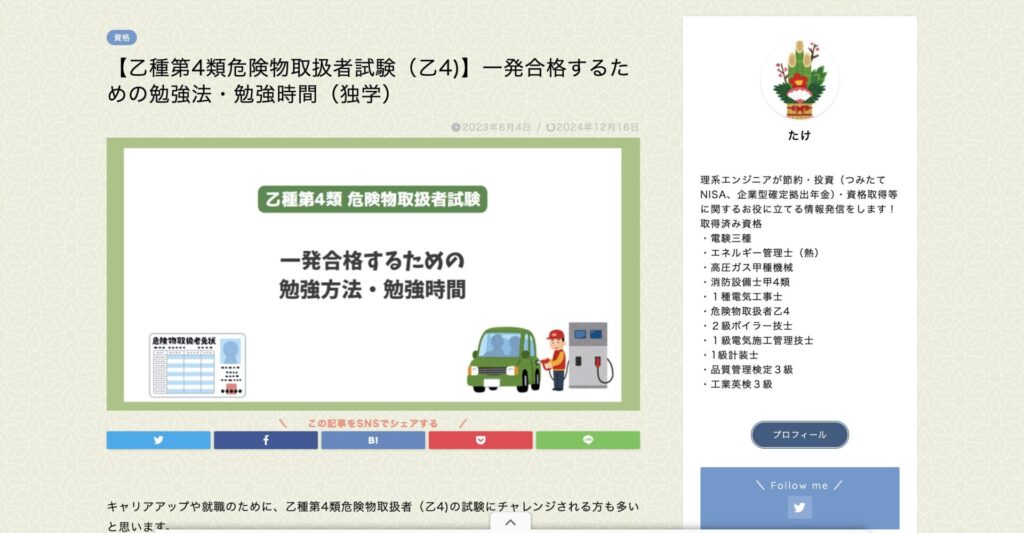
このブログの大きな特徴は、参考書は「1冊のみで十分」という明確な方針を示し、「過去10年間に出題された535問が収録」「テキスト・過去問・解説を1冊でカバー」「出題頻度に応じて★印がついている」という、「乙種4類危険物取扱者試験」テキストの具体的なメリットが画像を交えて丁寧に説明されている点です。
勉強方法では「テキストをさらっと読む→過去問を解く→解説を確認→2回繰り返す→付箋を貼った問題を集中学習する」という6ステップの具体的な手順が示されており、「1日10分でも毎日勉強する」「間違えた問題はその日のうちにもう一度解く」といった記憶定着のコツも提供されています。
勉強時間は「40~50時間、試験1ヶ月~3週間前から開始」という現実的な目安が示されており、忙しい社会人にとって実現可能な学習計画が立てやすいブログです。
27:30代のじゆうちょう
次にご紹介するのは「30代のじゆうちょう」です。試験5日前に勉強を開始した筆者が、危険物乙4に5日間の短期学習で合格した体験を、リアルタイムの備忘録としてユーモアを交えて記録したブログで、超短期合格の現実的な方法論が特徴です。

「乙4攻略サイトの丸写し」「YouTube動画のリピート視聴」「寝る前30分の確認テスト」という3つの勉強方法を1日4時間半×5日間で実践し、乙4攻略サイトの42項目を完走するために「1日12項目進める」という計画立案が示されています。
お風呂中やご飯中も常に動画を流す隙間時間の活用方法も提示されており、実行可能な具体的手法が提供されています。
28:資格独学取得ブログ〜なめこの資格体験記〜
「資格独学取得ブログ〜なめこの資格体験記〜」は中学で理科が得意だった筆者が危険物乙4に合格した体験を綴ったブログで、勉強時間の詳細な記録と、試験当日の心理状態を含めた包括的な情報が特徴です。

試験日まで約1ヶ月半を4つのフェーズに分け、各時点での予想問題成績が詳しく記録されており、法令がボトルネックだったため9日前から「法令特化モード」に切り替えた学習戦略が示されています。
総勉強時間は約16時間半と現実的で、試験終了時の「09-06-03」という不安な手ごたえから実際の結果が「法令60%、物理化学80%、消火性質80%」というギリギリ合格だったという落差が印象的です。
免状取得までの費用(計8,495円)も詳しく示されており、コストと時間を意識した受験準備の参考になるブログです。
29:kiki blog
続いてご紹介するのは「kiki blog」です。危険物乙4の科目免除者や甲種受験者向けに、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」を詳しく解説するブログで、特に危険物の分類と特性を体系的にまとめた専門的なコンテンツが特徴です。

このブログの大きな特徴は、水溶性・非水溶性の危険物を「朝は特別な水を飲もう」「汗をかいたから水を飲んでスピンしよう」といった工夫された語呂合わせで暗記しやすくしている点です。
液比重、消火剤、各品名ごとの性質(色、引火点、刺激臭など)が詳細に整理されており、甲種受験を視野に入れた充実した情報が提供されています。
30:のぼゆエンジニアリング
次にご紹介するのは「のぼゆエンジニアリング」です。化学の基礎学力がほぼゼロの状態から危険物乙4に合格した筆者が、効果的な勉強方法と参考書を詳しく紹介するブログで、初心者向けの段階的学習アプローチが特徴です。

このブログの大きな特徴は、高校化学基礎の参考書から始める「事前学習」を推奨している点です。
化学に苦手意識のある受験者向けに、周期表の見方から化学の基礎を学んだ上で、乙4テキストに取り組む学習順序が示されており、スケジュール図を交えて1ヶ月の対策計画が提示されています。
31:Mr.テレビっ子!
「Mr.テレビっ子!」は文系の筆者が危険物乙4に2度目の受験で合格した体験を綴ったブログで、テキスト選びの重要性と個人の学習スタイル適応の実例が特徴です。
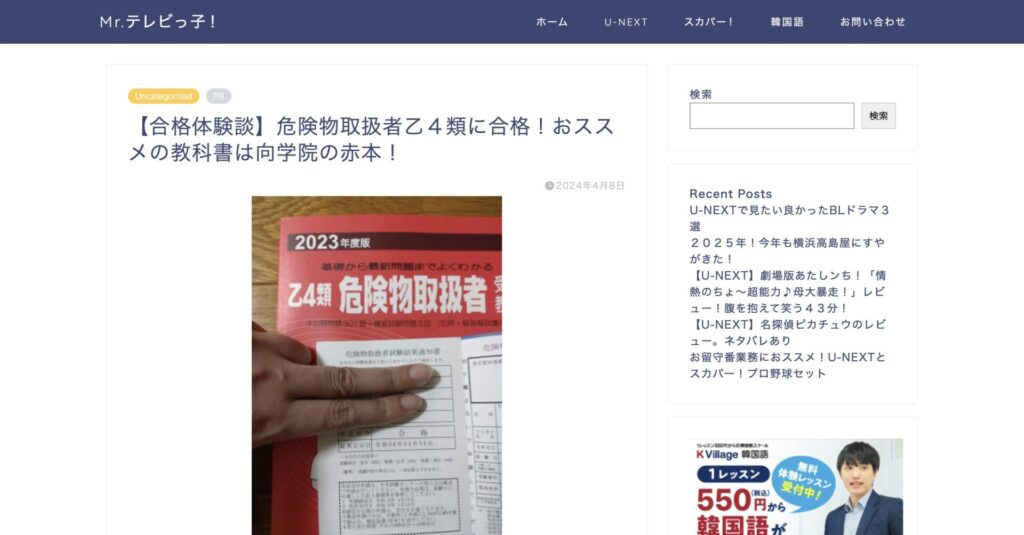
このブログの大きな特徴は、1度目の受験で不合格だった経験から、向学院の「赤本」に切り替えたことで合格に至った体験が示されている点です。
ユーキャンのフルカラー印刷では友人は合格したが筆者は不合格、赤本の白黒印刷では筆者が合格という対照的な結果から、「自分の覚えやすいテキストを選ぶことが重要」というメッセージが伝わってきます。
32:資格と独学のブログ
「資格と独学のブログ」はアーリーリタイア後にセルフスタンドの給油監視アルバイトを目指す40代筆者が、危険物取扱者乙種4類に合格した体験を綴ったブログで、シンプルで効率的な学習方法が特徴です。

このブログの大きな特徴は、テキスト2冊のみで合格した実績が示されている点です。
「10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格」と公論出版の過去問集を使い、過去問を3周解くというシンプルな学習戦略が提示されています。
テキストに付属の丸暗記ノートがスマホやタブレットでも使え、1時間で1回転できるため通勤時間の活用が可能であることも強調されています。
筆者は「9割以上解けた感じ」という試験の手ごたえを共有しており、「短期間で合格したい方は『すい~っと合格』、ゆっくり時間をかけたい方は公論出版の過去問集」という選択肢も提示しています。
また、テキストの誤植を確認すべきというアドバイスや、「10日で合格」は学生向けで社会人は2週間~1ヶ月かかるという現実的な学習期間も示されており、40代からの資格取得を考える受験者にとって参考になるブログです。
33:CookingPapa.work
「CookingPapa.work」は、転職を視野に入れながら危険物乙4に合格した筆者が、約19時間という短期間での合格体験を共有するブログで、YouTubeと問題集を組み合わせた効率的な学習方法が特徴です。

このブログの大きな特徴は、「あさと」さんと「ケムマスター」さんのYouTube動画を活用したスキマ時間学習が紹介されている点です。
学習の流れは「YouTubeで全体像を把握→テキストで基礎確認(深くやりすぎない)→問題集を繰り返し解く」というシンプルな構成で、暗記中心の試験特性を踏まえた戦略が示されています。
筆者は「問題を解く→解説を読む→間違えたところを重点的に復習」という反復学習の重要性を強調しており、「化学や計算が苦手でも大丈夫。乙4の試験はほぼ暗記なので、しっかり覚えれば誰でも合格できる」と励ましています。
また、タンクローリーや工場での求人で採用優遇されるという実用的なメリットも紹介されており、転職や実務での活用を考える受験者にとって参考になるブログです。
34:コレハジ
「コレハジ」は36歳でガソリンスタンド勤務中に危険物乙4に一発合格したゆうたさんの体験談を紹介しており、働きながらの短期合格を目指す受験者に実践的なアドバイスを提供しています。

このサイトの特徴は、「10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格」のテキストと無料アプリ「危険物取扱者乙4種」を組み合わせた低コストな学習法が紹介されている点です。
YouTubeの「優しい乙4対策講座」で指定数量の語呂合わせを参考にし、「図解でわかる危険物取扱者」サイトで苦手分野を補強するなど、複数の無料リソースを活用した戦略が示されています。
勉強順序は「物理・化学の基礎→性質・消火→法令」という流れで、法令は出題数が多いため最後に学習することを推奨しており、「問題傾向をよく知ることが重要」「難しい問題は捨てることも一つの手段」という効率重視のアドバイスが特徴です。
35:タクテク2
「タクテク2」はネットワークスペシャリストなど複数の国家資格を取得してきた筆者が「友人から参考書をタダで貸してもらえたから」という軽い動機で危険物乙4に挑戦した体験を綴るブログで、率直な難易度評価と効率的な学習戦略が特徴です。
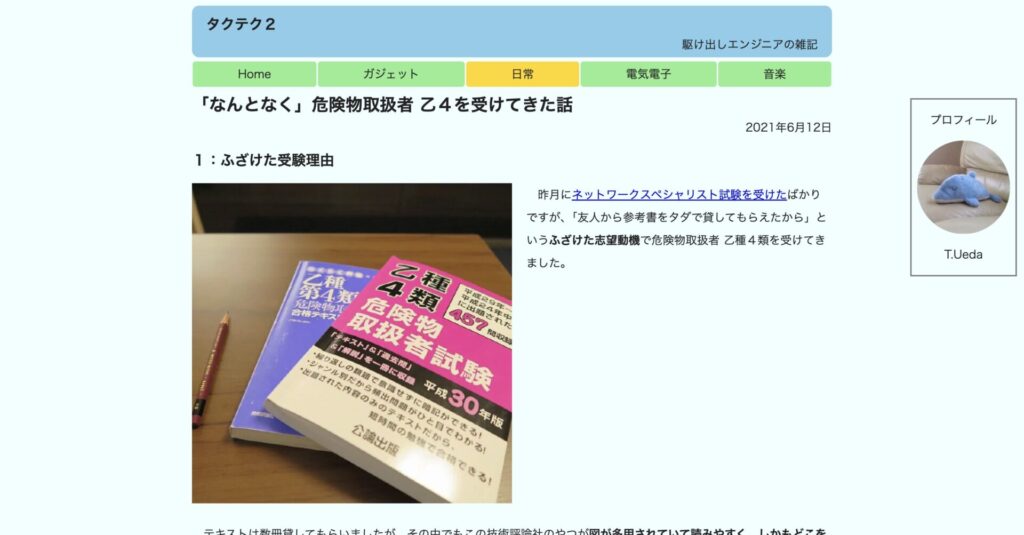
このブログの特徴は、学習期間1か月(実質1週間程度)で法規94%・その他100%という高得点で合格した実績と、「正直に言うと余裕だった」という率直な感想が示されている点です。
技術評論社のテキストを使用し、「法令は無理やり覚えて試験後に忘れる、物理・化学は高校化学の記憶でほぼ対応可能、性質・消火は上2つの合わせ技」という割り切った学習方針が提示されています。
また「問題数35問に対し試験時間2時間は時間設定を間違えている」として30分で途中退出したエピソードや、「覚えていないとどうしようもない問題がほとんど」という試験特性の指摘も特徴で、短期間で効率的に合格したい受験者や他の難関資格と比較した難易度を知りたい方にとって参考になるブログです。
36:Chem-Station
「Chem-Station」は、化学ポータルサイトの代表者が平成11年に危険物乙4を受験した体験記で、失敗談や苦労した点も率直に語られており、受験者のリアルな心境が伝わる内容が特徴です。

このサイトの特徴は、「これで合格 乙種危険物取扱者重要問題集」(新星出版社)を使用し、約1か月の学習で合格した体験が詳細に記録されている点です。
法令分野で「数字だけが違うきわどい問題が多く挫折気味」「毎日30分もできない」という苦戦の様子や、物理・化学分野は「なめてんのか?というくらい簡単」と飛ばした判断、前日のファミレス徹夜で「途中で眠くなって挫折」というエピソードなど、完璧ではない学習過程がリアルに描かれています。
37:Recommend Task
「Recommend Task」はメーカー研究者として働く筆者が危険物取扱者(甲種&乙4)に合格した体験記で、理系職種における資格の位置づけや甲種と乙4の選択基準が詳しく解説されているのが特徴です。

甲種の勉強時間は約100時間(理系出身者)、乙種は50〜100時間が目安とされ、「わかりやすい!甲種危険物取扱者試験」1冊のみで合格した実績が紹介されています。
難易度は「乙4を難易度1とすると甲種が2〜3」と相対評価され、合格率が乙4で40%前後、甲種で30%前後という数値も示されています。
「危険物の性質」科目が「正直一番キツかった。覚える量が半端じゃない」という率直な感想や、「ノートにまとめながら覚えた方が効率的」という具体的なアドバイスも特徴で、メーカー就職や転職を目指す理系の受験者にとって参考になるサイトです。
38:趣味は資格です
「趣味は資格です」は、資格ブロガーことパパが「人気の資格だから」という興味本位で危険物乙4を受験し、CFPと並行しながら約46時間の学習で合格した体験記で、詳細な学習スケジュールと申込から免状取得までの手順が丁寧に解説されているのが特徴です。

このサイトの特徴は、1ヶ月60時間を想定した具体的な学習スケジュールが日割りで示されている点です。
「ユーキャン速習レッスン」で1週間(1日37ページ)かけて全体像を把握し、「公論出版の過去問題集」を3週間で3回転(1日80問程度)するという明確なプランが提示されています。
「語呂合わせの箇所は適宜見直して暗記に用いる」「不得意分野を作らないように勉強時間の配分に気をつける」という実践的なアドバイスも特徴です。
39:脱線おじさんの独学記
「脱線おじさんの独学記」は、危険物乙4取得後に科目免除を利用して1・2・3・5・6類に挑戦した筆者が、「これが最適解だった」と振り返る効率的な勉強法をパワーポイント形式で解説するブログで、視覚的にわかりやすい学習スケジュールが特徴です。
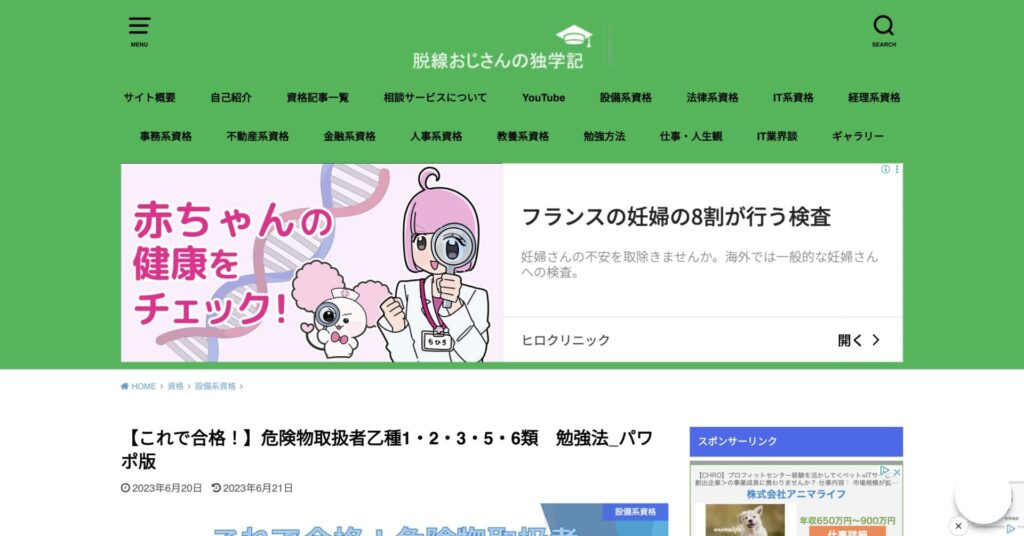
このブログの特徴は、科目免除で「危険物の性質」のみを受験する場合の学習プランが約15時間(2週間程度)と具体的に示されている点です。
「ユーキャンの速習レッスン」でインプット(1〜2周)、「公論出版の過去問題集」でアウトプット(最低2周以上)、試験前の総仕上げという3ステップが明確に提示されています。
「語呂合わせを念仏のように復唱して暗記」「どうしても分からないところは解答暗記で逃げてOK」「完璧主義になる必要はない」という実践的なアドバイスも特徴です。
40:学習雑記帳
「学習雑記帳」は2年半で16個の資格を取得した筆者が危険物乙種3・4・5・6類に合格した体験記で、類ごとの難易度比較と科目免除の有無による勉強時間の違いが具体的に示されているのが特徴です。

このブログの特徴は、「公論出版の過去問題集」を使用し約50時間(3週間・1日2〜3時間)で4つの類に合格した実績と、勉強時間の目安が「乙種未保有者で30〜70時間、性質・消火のみで5〜15時間」と明確に示されている点です。
類ごとの難易度を「第2類がかなり簡単、第4類と第5類が難しめ」と相対評価し、「乙4の合格率が38.6%と低いのは会社からの指示で受験しあまり勉強していない人が多いから」という分析も提示されています。
「問題の的中率は8割程度。参考書を8割正解できるレベルで本番ではギリギリ、全問正解なら余裕で合格」という具体的な目安や、「テキスト部分は全体的な理解に利用し、細かいところは覚えなくてOK。問題部分をとにかく周回する」という効率重視の学習方針が特徴で、複数の類を同時取得したい受験者や甲種受験資格取得を目指す方にとって参考になるブログです。
41:可能性は無限大
「可能性は無限大」は「気まぐれ」という動機で危険物乙4を受験した筆者が、3週間・約50時間の詰め込み学習で合格した体験記で、「気合だけの合格」というタイトル通りの率直な内容が特徴です。

文系で化学が大の苦手だった筆者が「エイヤーという気合」で丸暗記により合格した実体験が紹介されています。
使用教材は2冊のみで、テキストを3周し模擬試験問題集を解くというシンプルな学習方法が示されています。勉強期間は約20日(3週間)で勉強時間は50時間程度と具体的な数値も記載されています。
受験のきっかけが「完全に気まぐれ」「もしかしたら何かの役に立つかもしれない」という正直すぎる動機や、「業務で使用される方はしっかりと理解してください」という注意書きを繰り返している点も特徴的で、完璧な理解よりも合格を優先したい受験者や、化学が苦手でも合格できることを知りたい方にとって参考になるブログです。
42:fukuzublog
「fukuzublog」は、消防設備士乙種第6類受験をきっかけに危険物乙4を受験し一発合格した筆者が、独学での合格方法を詳細にまとめたブログで、複数教材の使い分けと具体的な勉強手順が特徴です。
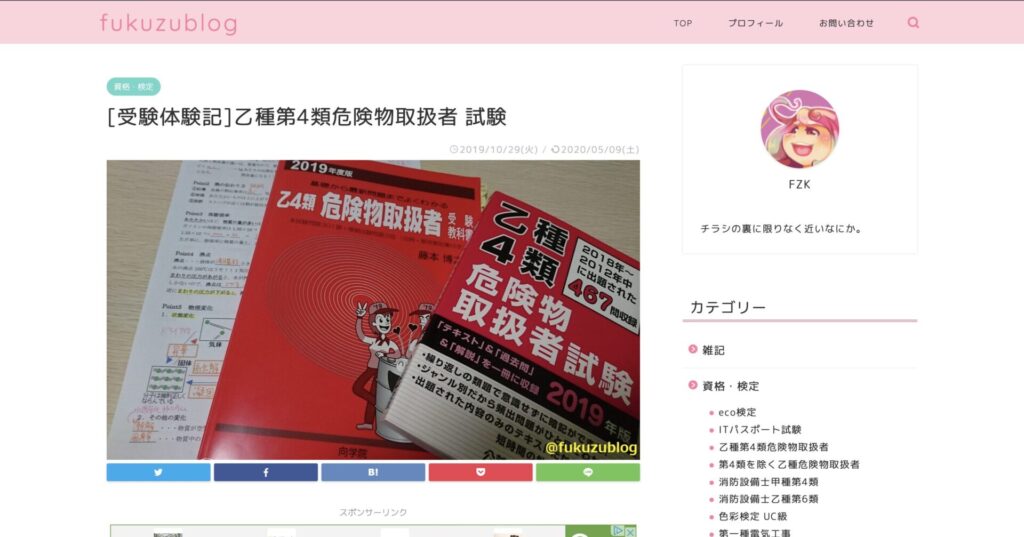
このブログの特徴は、「教科書として1冊、過去問集として1冊、最低でも2冊準備するのが良い」という明確な教材選定方針が示されている点です。
赤本を教科書として使用し、「公論出版のピンク本」を過去問集として活用、さらにYouTube「電験合格」の危険物乙4講座を併用する学習戦略が提示されています。
勉強手順は「教科書を1回通す→YouTube講座を視聴しながら配布プリントをやる→苦手分野を過去問集で補強」という段階的なプランが示されています。
43:強欲な青木&消防設備士オフィシャルサイト
「強欲な青木&消防設備士オフィシャルサイト」は、高専3年生(17歳)の時にガソリンスタンドのバイトで時給100円アップを目指して危険物乙4を受験し「まぐれ」で合格した筆者が、友人は落ちたという対照的な結果も含めて体験を綴るブログで、テキストなしでの受験エピソードと現代のデジタル学習環境への言及が特徴です。

このブログの特徴は、「友人と一緒に受験申込をしたがテキストも買っていなかった」という破天荒なエピソードと、一緒に受けた友人だけが落ちたという結果が率直に語られている点です。
筆者は「まぐれで合格」と謙遜しながらも、後に電験三種やAI・総合種などの難関資格を取得した経験から「スマホで電子書籍のテキストや過去問を見ていたからこそ合格できた」と振り返り、現在のスマホ学習環境(月額980円の授業動画など)を高く評価しています。
44:夢みる資格研究所 乙4支所
「夢みる資格研究所 乙4支所」は、文系で物理・化学をまともに勉強してこなかった筆者が、フォーサイトの通信講座を使い36.5時間(約1ヶ月)の勉強で危険物乙4に合格した詳細な体験記で、日別の勉強記録と時間配分が具体的に記録されているのが特徴です。
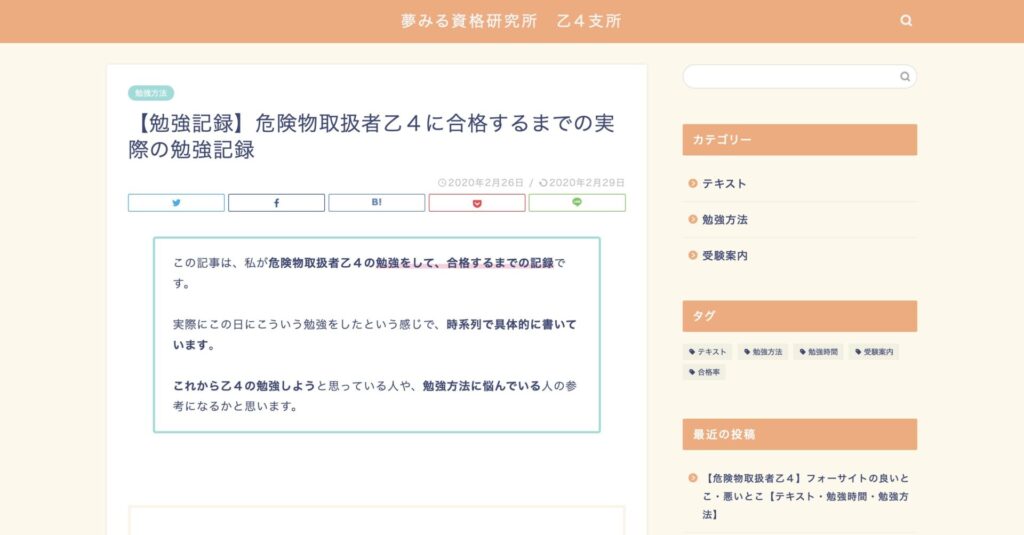
学習プロセスは、
- 講義動画7時間
- 問題集1周目12.5時間
- 過去問2時間
- 問題集2周目6.5時間
- テキスト通読2.5時間
- 模擬試験1.5時間
- 知識整理3.5時間
- ネット模試1時間
という構成で、各段階での気づきや反省点も率直に記録されています。
独学とフォーサイト(約2万円、現在は1万円)を比較検討した経緯や、「講義動画は理解のしやすさが違う」「ペースメーカーになる」という通信講座のメリットも詳しく解説されています。
45:ASATO BLOG
「ASATO BLOG」の「【実際の受験者の声あり】危険物乙4の合格率と難易度について解説」という記事では、危険物甲種資格保有者で動画講座を主催するあさとさんが、合格率30〜40%という数値と実際の受験者インタビューをもとに危険物乙4の難易度を解説しており、化学の学習経験の有無による難易度の違いが強調されています。

不合格者へのインタビューで「化学が難しかった。これまで化学を勉強してこなかったので計算問題が全くわかりませんでした」という生の声が紹介されており、試験の3つのパート(法令・物理化学・性質消火)のうち物理化学が鍵になることが具体的に説明されています。
46:電気エンジニアのツボ
「電気エンジニアのツボ」は、すでに危険物乙4を取得済みの筆者が、スタディングのオンライン講座を無料体験し、受講者4万人超の人気講座について徹底解説するサイトで、社会人の時間不足問題に焦点を当てた学習方法の提案が特徴です。

このサイトの特徴は、料金5,480円(合格お祝い金2,000円適用で実質3,480円)のスタディング「危険物取扱者乙種4類合格コース」が詳しく紹介されている点です。
実際の受講者の口コミ(「約1か月間、通勤電車で勉強して合格」「PCで毎日2時間、外出時はスマホで2か月半続けて合格」など)と、筆者自身の無料体験レポートが組み合わされています。
「動画は通常から3倍速まで選択可能」「1つの動画が20分前後で隙間時間に最適」「間違えた問題のみを解く機能がある」という具体的な機能紹介も特徴です。
47:jjpapa.blog
「jjpapa.blog」は2022年11月に危険物乙4を受験し、2ヶ月・合計52時間の独学で法令満点を含む一発合格を果たした筆者が、無料リソースを活用した勉強法を紹介するサイトで、YouTube動画講座の活用が大きな特徴です。

このサイトの特徴は、赤本とYouTube「大分工業高等学校の乙4危険物取扱者試験対策講習会」、無料web模擬試験の3つを組み合わせた学習方法が詳しく紹介されている点です。
平日30分・休日2時間という現実的な勉強時間配分が示され、大分工業高等学校のつつみ先生の動画について「ユーモアのある方で『絶対に受かる』と自信を与えてくれた」「高校生の日常生活を思い出しながら勉強するのも悪くない」と具体的に評価しています。
48:DODO BLOG
「DODO BLOG」は危険物乙4を前日8時間(実質6時間と記載)の超短期集中学習で合格した筆者が、「本を読めば誰でも合格できる資格」と断言する体験記で、極端に短い勉強時間での合格実績が特徴です。

このブログでは、「10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格」1冊のみを前日に繰り返し読んで暗記するという究極的にシンプルな学習方法が紹介されています。
「すい~っと合格は満点を目指すものではなく、合格最低点付近での合格を最短最速で目指す参考書」「試験範囲の全てをカバーしていない」という率直な評価も示されており、「どうしても不安な方は他の参考書で補った方がいい」というアドバイスも添えられています。
49:続・理系院卒から目指す保育士試験合格への道
「続・理系院卒から目指す保育士試験合格への道」は、初回受験で法令40%という悲惨な結果で不合格となり、リベンジ受験で法令66%のギリギリ合格を果たした筆者が、失敗から学んだ教訓と使用教材の率直な評価を綴るブログで、不合格体験からの逆転合格ストーリーが特徴です。

このブログの特徴は、初回不合格の具体的な点数(法令40%・物理化学70%・性質消火80%)が公開され、「どうしてこうなった」と自虐的に振り返っている点です。
1回目はテキストのみで受験し不合格後に問題集を追加購入した経緯が紹介され、「テキストだけでの合格は正直かなり厳しい。演習問題の難易度が相当低めに設定されている(特に法令)ため実戦では通用しない」という痛烈な評価が示されています。
対照的に追加購入した問題集については「しっかり硬さがあり、必要な知識もまとまっているため問題集のみで十分では?」と高く評価しています。
50:マイカ@たつおブログ
「マイカ@たつおブログ」は実際に10日ほどで危険物乙4を取得した筆者が、「10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格」のテキスト1冊のみでの合格体験をもとに、メリット・デメリットを詳しく解説するブログで、忙しい社会人向けの効率的な学習アプローチが特徴です。

このブログの特徴は、「すい~っと合格」のメリットとして「重要なポイントが分かりやすく編集され合格ラインを突破できる」「過去問130問と本試験形式2回分が付属で問題集を別途購入不要(1,760円のみ)」「丸暗記ノートと同内容のスマホアプリで人目を気にせず勉強できる」という3点が具体的に挙げられている点です。
一方デメリットとして「物理化学は情報が少ない」「最新情報がメモ書きのような紙で付属し紛失リスクがある」という率直な指摘もされています。
51:Anon Re:port
「Anon Re:port」には、「特に意味はない」という理由で危険物乙4に挑戦し、前日と当日の実質5時間程度の勉強で合格した筆者が、ユーモラスな語り口で超短期学習法を紹介する記事が掲載されており、徹底的に力を抜いた学習スタイルと「受かればいい」という割り切った姿勢が特徴です。

このブログの特徴は、「10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格」を使い、
- 参考書を折って勉強した雰囲気を出す
- 前日ひたすら音読
- 模擬テストも答えを見て覚える
- 当日の電車内も音読
という独特な学習法が紹介されている点です。
「100点取らせようとしてない参考書。100点取りたい人は絶対買ってはいけません」という評価や、「計算問題は全く公式すら暗記していない。ぽっくん文系だから」という開き直りも示されています。
「試験なんて満点取らなくていい。受かればいいんです」「資格は取ったもん勝ち」という割り切った姿勢が特徴で、勉強が苦手で最小限の努力で合格したい受験者にとって参考になるブログです。
52:きんげの資格部屋
「きんげの資格部屋」は試験3日前から慌てて勉強を始め、筆記用具や消しゴムを忘れるなどのハプニングにも見舞われながら合計18時間の勉強で危険物乙4を受験した体験記で、準備不足の中での奮闘ぶりが率直に綴られているのが特徴です。

このブログの特徴は、「試験3日前に慌てて図書館に通い、テキストを諦めて模擬試験問題集とチェック問題に的を絞った」という学習方針転換が描かれている点です。申込2ヶ月前に7時間勉強後放置し、試験3日前から再開という詳細な記録も示されています。
試験当日は「筆記用具を忘れてコンビニに駆け込んだら消しゴム付いてない鉛筆だった」「もう諦めモード」という失敗談や、「法令は自信をもってマークできたのは15問中3問だけ。あとは消去法とカン」という正直な感想も語られています。
「手ごたえから合格は期待できないので、早速次の試験に向けてテキストを最初から読み始めた」という前向きな姿勢も特徴で、準備不足でも挑戦する受験者にとって参考になるブログです。
53:HOSIGO
「HOSIGO」の「危険物乙種第4類資格のおすすめ勉強法」という記事では工業高校や自動車整備の専門学校の学生でもない限りゼロからのスタートとなる危険物乙4に一発合格を果たした筆者が「過去問をひたすら解く」というシンプルな勉強法を紹介しています。

この記事の特徴は、「間違えた問題の正しい答えだけでなく、問題も一緒に最低5回はそのまま書き写す」「チラシの裏にひたすら書いて覚える」「テキストで間違った分野の解説を納得するまで読む」という3段階の学習プロセスが紹介されている点です。
「何度も書くと次に解く時に『これ何回も書いたやつだ!』という記憶が呼び起こされ、自然と答えが浮かんでくる」という効果が説明されています。
「地頭が良い人はアプリでサクサク覚えられるが、私の勉強法は勉強が苦手だった人におすすめ」という率直な表現も特徴で、デジタルツールよりも手を動かして覚えたい受験者にとって参考になるブログです。
54:火消しの雑記帳
「火消しの雑記帳」は現役消防士のマツナガさんが、消防学校の初任教育中に受験する危険物乙4について解説するサイトで、消防士にとっての実務的な必要性と消防学校での受験システムが特徴です。

このサイトの特徴は、「消防士は消防車や救急車にガソリン・軽油を給油するため乙種4類が必須」という職業上の明確な理由が示されている点です。
消防学校では8時間の授業とテキスト・問題集が配布され、8月中に学校内で試験が実施され、この初回受験は公費のため無料であることが説明されています。
合格率は6割程度で、不合格者には9月中の土日に追試が実施されるものの自費負担となり、「もし初任教育中に取得できないと現場に配置されたときにかなり恥ずかしい思いをする。現場では資格保持者リストを毎年確認するから」という現実的な事情も語られています。
55:30代からのビルメン転職成功ブログ
「30代からのビルメン転職成功ブログ」は、知識ゼロから2週間の勉強で危険物乙4に一発合格した筆者が、ビルメン4点セットの1つとして乙4取得を目指す方に向けた実践的な勉強法を紹介するブログで、短期集中型の学習戦略が特徴です。

このブログの特徴は、「10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格」を使用し、10日間スケジュール(実際の暗記期間は4日間のみ、残りは演習問題)を2週間に余裕を持たせて実践した学習法が紹介されている点です。
「苦手な問題は捨てる」という割り切った戦略も提示され、「全35問中21問正解すれば合格。分からない問題を14問まで捨てても合格可能」「イオン化傾向の問題を捨てたが試験結果に大したダメージにならなかった」という具体例も示されています。
56:PikoPikoBlog
「PikoPikoBlog」は、1回目の受験で不合格後、2週間の勉強で2回目に合格した筆者が、「10分しか集中力が続かない」という正直な学習環境の中で工夫した勉強法を日別の詳細記録とともに紹介するブログで、独自の語呂合わせ作成と超短時間学習サイクルが特徴です。
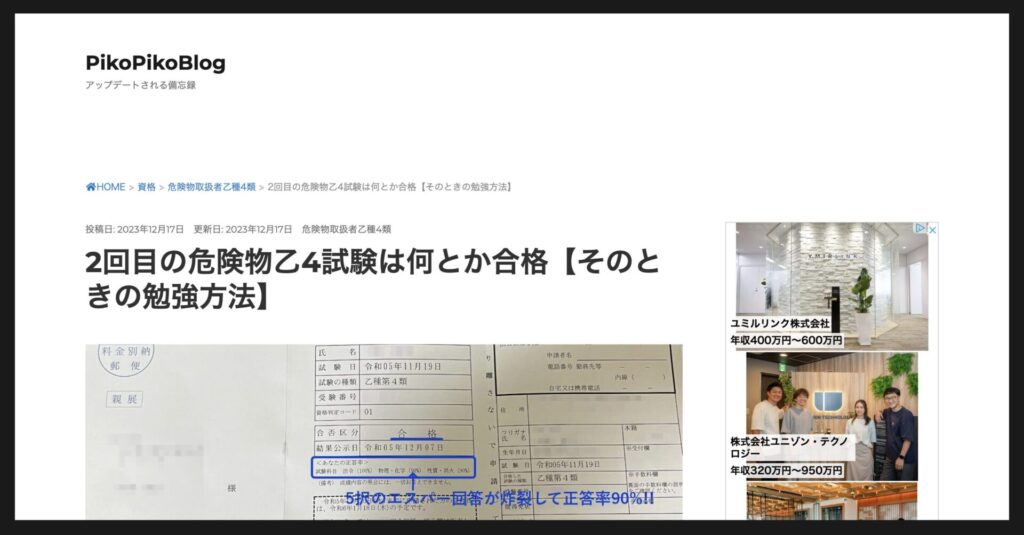
このブログの特徴は、14日間の学習内容が日別・時間別に詳細に記録され、「10問解いて答え合わせをしたら約10分。YouTube視聴で10〜20分休憩」という独特な学習サイクルが紹介されている点です。
ユーキャンの「10日で合格テキスト」とチャレンジライセンスのテキストを使用し、覚えにくい表を独自の語呂合わせで暗記する方法が詳しく解説されています。
「さかじいじこさ、ここぶえぶえ」(危険物の分類)、「といあにさしどう」(危険物第4類)など、試験で3問役立った自作語呂合わせが具体的に公開されています。
57:オクラビット
「オクラビット」の「危険物乙4の過去問はそのまま使いまわし?おすすめ問題集で対策を!」という記事では、独学で危険物乙4に一発合格した筆者が、問題用紙持ち帰り厳禁という試験の特性と「年間250回も実施される試験で毎回違う問題を作成するのは不可能」という論理的分析から、過去問使い回しの実態とおすすめ問題集が紹介されています。
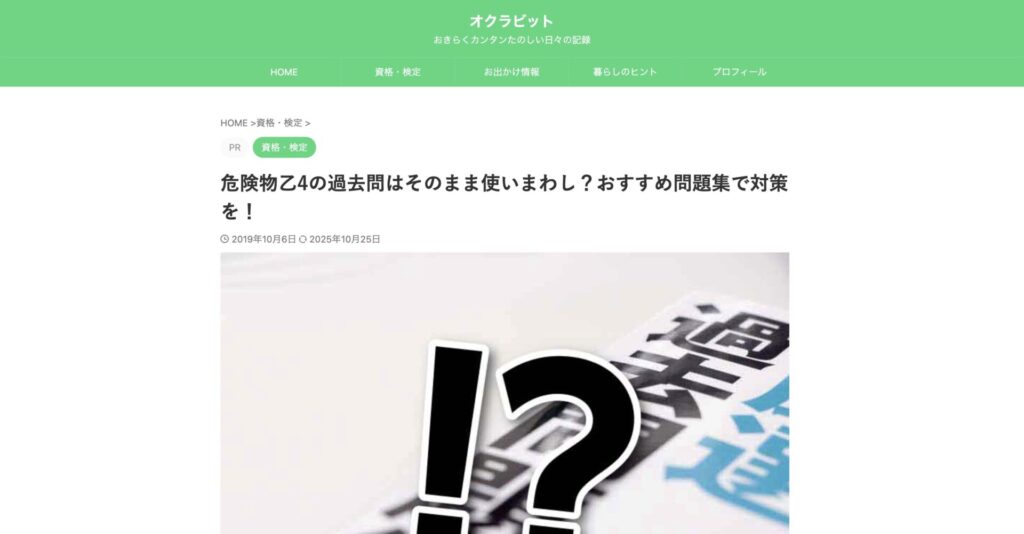
このブログの特徴は、実際にジュンク堂書店あべのハルカス店で調査したうえで「公論出版の乙種4類危険物取扱者試験」と「オーム社の過去問パターン分析!乙4類危険物試験 解法ガイド」の2冊をおすすめしている点です。
特にオーム社版については、著者の鈴木幸男氏が「30年以上講師を務め、年間約15回も実際に受験して問題を覚えて帰ることで分析している」というエピソードが紹介され、「やはり年に何度も同じ問題が出題される」という証言が示されています。
58:いいことあるよ!
「いいことあるよ!」には、危険物乙4に独学で一発合格した筆者「まるにい」が、問題集を繰り返し解くシンプルな勉強法を紹介する記事が用意されており、テキストを後回しにして最初から問題を解き始めるという独特なアプローチが特徴です。
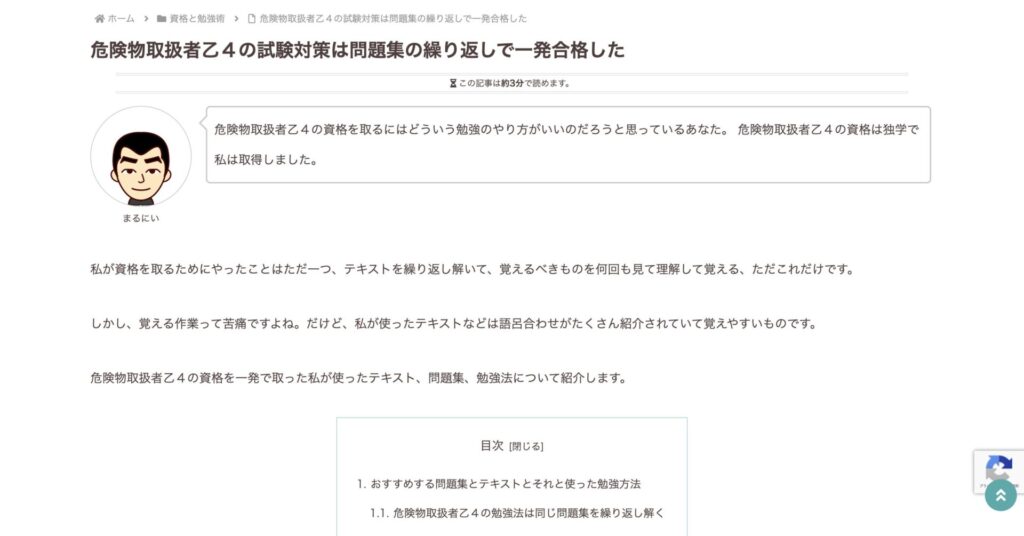
このブログの特徴は、「初めて勉強を始める時でもテキストを開くのではなく、始めから問題を解いていく。知識がないわけだから分からなくて当たり前」という割り切った学習スタイルが示されている点です。4回転の学習サイクルが提示されており、
- 問題の程度を把握
- 1問ずつ理解し語呂合わせで覚える
- ひたすら繰り返す
- 間違えた問題だけを徹底対策
という段階的なプロセスが説明されています。使用教材はカラーでイラストもあり語呂合わせが多く紹介されているテキストと問題集の併用が推奨されています。
59:技術資格オープンラボ
「技術資格オープンラボ」には、危険物取扱者の甲種・乙4について、受験者の背景ごとに必要な勉強時間を詳細に分類し、効率的な勉強方法を解説する記事が用意されています。
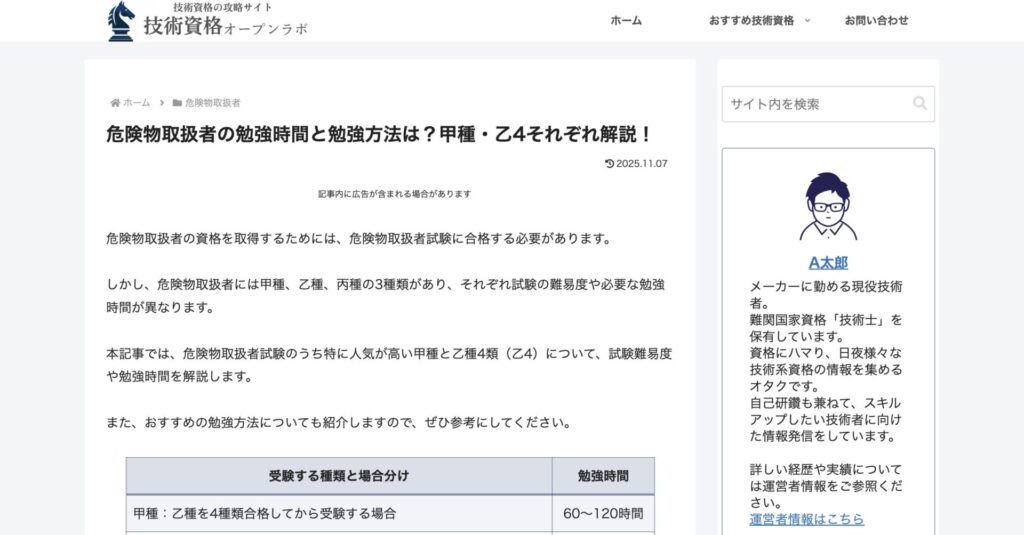
この記事の特徴は、勉強時間が5つのケースに分類されている点です。
「甲種(乙種4類合格後):60〜120時間」「甲種(理系大卒):100〜150時間」「乙4(理系大卒):50〜80時間」「乙4(文系):70〜100時間」という具体的な目安が示されています。
科目別特性も整理され、「法令と性質・消火は暗記もの」「物理・化学は計算が必要で理解が必要」という明確な区別が示されています。
「危険物取扱者試験は過去問が公開されていないため『過去問を繰り返し解く』という必殺技が使えない」「中学高校の教科書での勉強は効率が悪い」という注意喚起も特徴で、自分の背景に合わせた学習計画を立てたい受験者にとって参考になるサイトです。

