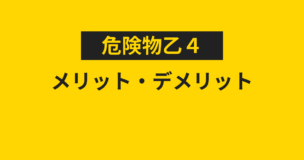
危険物乙4(乙種第4類危険物取扱者)の取得を目指している人の中には危険物乙4のメリット・デメリットが気になっている人もいるでしょう。
今回は日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4のメリット・デメリットを10個ずつまとめたので、それらをご紹介していきます。
危険物乙4を受験予定の人はぜひチェックしてみてください。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
危険物乙4のメリット10個まとめ
危険物乙4のメリットは以下の10個です。
- 就職・転職に有利
- 資格手当がもらえる可能性がある
- 仕事の選択肢が広がる
- ガソリンスタンドでの勤務に役立つ
- 消防法の知識が身につく
- 独立開業の可能性が広がる
- 仕事の幅が広がり、昇進につながることもある
- 国家資格なので、一生使える
- 危険物の知識が日常生活でも役立つ
- 比較的取得しやすい国家資格である
それぞれ詳しく解説していきます。
1:就職・転職に有利
危険物乙4は多くの業界で需要が高く、就職や転職に有利な国家資格です。
※「危険物乙4は国家資格で履歴書に書ける!書き方・正式名称は?」もぜひ合わせてご覧ください。
特にガソリンスタンドや工場・倉庫・運送業・化学プラントなど、危険物を取り扱う職場では必須資格となる場合もあります。
危険物乙4を保有していることで応募できる求人の幅が広がりますし、無資格者と比較すると採用率はもちろん高まります。
また、危険物乙4は危険物を適切に扱える証明にもなるため、安全管理や品質管理の仕事にも活かせます。
未経験でも危険物乙4を保有していることで即戦力として評価されるケースもあり、特に転職市場では大きな強みになります。
2:資格手当がもらえる可能性がある
危険物乙4を保有していると、職場によっては資格手当が支給されることもあります。
例えば、ガソリンスタンドや危険物を扱う倉庫・化学工場では月数千円〜1万円程度の手当が付くことも珍しくありません。
※「危険物乙4がガソリンスタンドで重宝される理由と具体的な業務内容・将来性を徹底解説」もぜひ合わせてご覧ください。
危険物乙4を保有しているだけで毎月の収入が増えるため、長期的に見ても大きなメリットとなります。
また、資格手当がある会社では危険物乙4保有者が優遇される傾向があり、昇進や昇給のチャンスが広がることもあります。
資格を活かして安定した収入を得たい人にとって、危険物乙4は取得するメリットが大きい資格の1つです。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
3:仕事の選択肢が広がる
危険物乙4を保有していることで、さまざまな職種に挑戦できるようになります。
例えば、ガソリンスタンドの給油業務や化学工場の設備管理・石油会社の倉庫業務・タンクローリーの運転手・船舶の燃料管理など、危険物を扱う仕事は多岐に渡ります。
特に物流や製造業では、危険物を安全に取り扱えるスキルが求められるため、危険物乙4があることで採用の可能性が高まります。
また、最近ではリチウムイオン電池の管理や、再生可能エネルギー関連の業務でも危険物乙4の知識が役立つ場面が増えており、新たな分野への進出も可能です。
4:ガソリンスタンドでの勤務に役立つ
ガソリンスタンドでは危険物を適切に管理するために、一定数の危険物乙4保有者が必要です。
そよって、危険物乙4を保有しているとガソリンスタンドでの勤務がしやすくなります。
特に、セルフスタンドでは給油監視業務を行うために危険物乙4保有者が必須となるため、危険物乙4を持っていることで採用される確率が高くなります。
また、スタンドの管理者や店長を目指す際にも、危険物乙4があることでキャリアアップしやすくなります。
ガソリンスタンドは未経験からでも比較的入りやすい業界なので、危険物乙4を活かして手に職をつけることができます。

5:消防法の知識が身につく
危険物乙4の取得過程では、消防法や危険物に関する法律について詳しく学ぶことになります。
これにより、危険物の適切な取扱方法や貯蔵・運搬時のルールを理解でき、安全管理のスキルが向上します。
特に、企業の安全管理部門や品質管理部門で働く場合は法律に基づいた管理が求められるため、危険物乙4の知識をそのまま活かすことができます。
また、火災や爆発事故を防ぐための知識も身につくため、危険物乙4は職場だけでなく日常生活でも役立ちます。
法律を理解することで、より安全な環境づくりに貢献できます。
6:独立開業の可能性が広がる
危険物乙4を活かして独立開業する道もあります。
例えば、灯油や軽油の販売業、危険物を保管する倉庫業、危険物取扱のコンサルティング業など、危険物乙4が求められるビジネスは多岐にわたります。
特に、地方ではストーブ用の灯油販売が盛んなため、小規模な燃料販売店を開業する人もいます。
また、ガソリンスタンドを経営する場合でも、危険物乙4を持っていることで事業をスムーズに運営できます。
資格を活かして独立を目指す人にとって、危険物乙4は大きなメリットをもたらす資格といえます。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
7:仕事の幅が広がり、昇進につながることもある
危険物乙4を保有していると、職場での役割が広がり、昇進のチャンスが増えることがあります。
例えば、工場や倉庫では危険物の管理者として責任のあるポジションを任されることが多く、管理職への道が開けます。
また、危険物乙4を保有していることで専門性が高まり、上司や同僚からの評価も向上しやすくなります。
上記でも解説しましたが、企業によっては危険物乙4を取得することで昇給の対象になることもあり、危険物乙4がキャリアアップの後押しとなる可能性が高いです。
8:国家資格なので、一生使える
危険物乙4は一般財団法人 消防試験研究センターが実施している国家資格です。
そのため、転職やキャリアチェンジの際にも有効で、一生涯活用できるのが大きなメリットです。
危険物乙4に合格すると「危険物取扱者免状」が交付されます。
「危険物取扱者免状」の写真の書換えは10年に1回必要ですが、問題等を起こさない限り資格が失効することはありません。
※「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」もぜひ合わせてご覧ください。
危険物乙4はどの業界でも使えるため、長期的に見ても取得する価値が高いメリットのある資格といえます。
また、いざという時のために持っておけば、再就職の際にも強みになります。
9:危険物の知識が日常生活でも役立つ
危険物乙4を勉強する過程ではガソリンや灯油の適切な取り扱い方法を学ぶことができるため、日常生活でも安全意識が高まります。
具体的には、家庭での灯油ストーブ使用時やガソリンを扱う場面で事故を防ぐための知識が身につきます。
また、災害時の燃料管理や適切な貯蔵方法を知っていることで、自分や家族の安全を守ることもできるようになります。
防災意識を高める意味でも、危険物乙4の知識はかなり役立ちます。

10:比較的取得しやすい国家資格である
危険物乙4は国家資格の中でも比較的取得しやすい資格です。
危険物乙4の試験範囲は決まっており、しっかり勉強すればほとんどの人が合格可能な難易度です。
※「危険物乙4の合格率推移!難しくなった?難易度は?難しいから諦める人も?」もぜひ参考にしてください。
また、独学でも合格を目指せるため、コストを抑えて取得できるのもメリットの1つです。
試験は全国の試験会場で毎月実施されているため、挑戦しやすいのも特徴です。
仕事をしながらでも取得しやすく、スキルアップを目指す人には最適な資格といえます。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
危険物乙4のデメリット10個まとめ
危険物乙4のデメリットは以下の10個です。
それぞれ詳しく解説していきます。
- 転職・就職が確実というわけではない
- 業務独占資格ではないため、必須ではない職場もある
- 資格手当が少ない、または支給されないことがある
- 試験に合格しても実務での即戦力になりにくい
- 受験にはある程度の勉強時間が必要
- 業界によっては危険を伴う仕事がある
- 資格を活かせる職場が限られる
- 資格を持っていると責任が増す
- 更新が不要なので、知識が風化しやすい
- 資格の取得費用と時間がかかる
1:転職・就職が確実というわけではない
上記でも解説した通り、危険物乙4はメリットが大きい資格ではありますが、持っているだけで必ず転職・就職が成功するわけではありません。
多くの企業では、実務経験や他のスキルと組み合わせて評価されるため、危険物乙4という資格単体でのアピール力は限定的です。
特に倍率が高い企業では、危険物の知識だけでなく、設備管理や品質管理などの実務経験が求められることもあります。
また、転職市場では資格よりも実際の業務スキルが重視される傾向があり、危険物乙4取得後に現場経験を積むことが重要になります。
危険物乙4だけでなく、フォークリフト免許や高圧ガス製造保安責任者などの関連する資格を取得できると、より有利に就職・転職を進めることができるでしょう。
2:業務独占資格ではないため、必須ではない職場もある
危険物乙4は医師や弁護士・公認会計士のような「業務独占資格」ではありません。
つまり、資格がなければ絶対にできない仕事があるわけではなく、現場によっては無資格者でも作業可能な業務が多いのが現実です。
例えば、ガソリンスタンドの給油業務では危険物乙4保有者が必要とされることが多いですが、倉庫や工場での作業では危険物乙4がなくても従事できることが多いです。
そのため、「危険物乙4を保有している=必ず仕事に活かせる」とは限らず、業界や職場によっては思ったより評価されないケースもあります。
危険物乙4取得の目的を明確にし、活かせる業界を選ぶことが重要です。
3:資格手当が少ない、または支給されないことがある
上記のメリットでも解説した通り、危険物乙4を持っていると資格手当が支給される職場もありますが、その金額は思ったより少ないことが多いです。
危険物乙4の資格手当の相場は月数千円で、高くても1万円です。
また、会社によっては資格手当がまったく支給されないこともあります。
そのため、「危険物乙4を取れば収入が増える」と期待していると、現実とのギャップを感じることもあります。
資格手当の有無は企業によって異なるため、資格を活かせる職場を選ぶ場合は、事前に求人情報をしっかり確認することが大切です。
4:試験に合格しても実務での即戦力になりにくい
危険物乙4を勉強する過程で危険物の性質や消防法などの知識を学ぶことができますが、実際の職場で必要な技能(機器の操作方法、安全点検の手順など)は身につきません。
※危険物の性質の詳細は「危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせで紹介!性質の問題例は?」をご覧ください。
そのため、危険物乙4を取得しても即戦力として評価されることは少ないです。
現場ではマニュアルに沿った作業が求められるため、資格よりも実際の業務経験が重視される傾向があります。
そのため、危険物乙4取得後はできるだけ早く実務に携わり、経験を積むことが重要です。
5:受験にはある程度の勉強時間が必要
危険物乙4は比較的取得しやすい国家資格とはいえ、事前の勉強は必須です。
危険物乙4の試験範囲は広く、以下の例題のように化学や物理に関する問題も出題されるため、理系科目が苦手な人は苦戦するケースもあります。
【例題】
比熱(s)、質量(m)と熱容量(C)の関係式として、正しいものを1つ選びなさい。
- C=sm
- C=sm2
- C=sm2 – m
- C=s/m
- C=m/s
【解答&解説】
正解は1・・・(答)です。
熱容量は「比熱 × 質量」で計算可能です。
※「危険物乙4の計算問題で必要な公式まとめと過去問に似た例題!難しい?捨てるのはあり?」もぜひ合わせてご覧ください。
独学での合格を目指す場合は40〜60時間程度の勉強時間が必要とされ、効率良く学習しないと落ちる可能性も十分にあります。
※「危険物乙4の勉強時間は40~60時間と言われてます!10時間の勉強時間で受かる方法とは?」もぜひ参考にしてください。
そのため、短期間で危険物乙4を取得したい人にとっては負担に感じることがあるでしょう。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば40〜60時間も勉強する必要はありません。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
6:業界によっては危険を伴う仕事がある
危険物乙4を活かせる職場はガソリンスタンドや化学工場・石油関連施設など、危険物を取り扱う環境が中心です。
火災や爆発のリスクが常に付きまうため、厳格な安全管理が求められます。
特に、高温・高圧の設備を扱う現場では事故のリスクが高く、常に慎重な作業が必要です。
また、責任者としてのプレッシャーを感じることもあり、安全管理への意識が低いと事故に巻き込まれてします危険性があるので十分ご注意ください。
7:資格を活かせる職場が限られる
危険物乙4が活かせる職種はガソリンスタンドや危険物を取り扱う倉庫・石油関連企業・化学工場などに限られます。
事務職やIT業界、医療・福祉系などの仕事ではほとんど活用できません。
※IT業界ではITパスポートという国家資格が役に立つことがあります。詳しくは「ITパスポート試験完全攻略サイト」をご覧ください。
現在の職業と関係がない場合、危険物乙4を取得するメリットは感じにくいでしょう。
危険物乙4を取得する前に、自分のキャリアと合致するかをしっかりと検討することが重要です。
8:資格を持っていると責任が増す
危険物乙4を保有していると、職場で危険物管理者としての責任を任されることがあります。
消防法や安全管理基準は遵守しなければならないため、ルール違反があれば責任を問われることもあります。
また、事故が発生した場合は危険物乙4保有者としての適切な対応が求められるため、プレッシャーを感じることも少なくありません。
9:更新が不要なので、知識が風化しやすい
危険物乙4は一度取得すれば再受験不要なので、その分、知識が風化しやすいというデメリットがあります。
特に、長期間実務から離れると、消防法の改正や新しい危険物の取扱基準について知らないままになってしまうこともあります。
なので、危険物乙4取得後も、定期的に学習を続けることが求められます。
10:資格の取得費用と時間がかかる
危険物乙4の受験には受験料5,300円(非課税)が必要で、参考書や問題集も購入するとさらに費用がかかります。
※「危険物乙4の受験料・費用は5,300円!値上げされた?支払い方法は?」もぜひ合わせてご覧ください。
また、上記でも解説した通り、危険物乙4に合格するには40〜60時間程度の勉強時間が必要なので、仕事や学業と両立しながら合格を目指すのは負担になることもあります。
危険物乙4に限らずですが、資格取得を考える際は費用対効果をよく検討することが重要です。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
今回は危険物乙4のメリット・デメリットを10個ずつまとめてみました。
危険物乙4の受験を検討している人は、ぜひ本記事でご紹介したメリットとデメリットを考慮してみてください。


