
危険物乙4(乙種第4類危険物取扱者)では「基礎的な物理学及び基礎的な化学」という科目が用意されています。
※本記事では「物理化学」と呼ぶことにします。
今回は日本で一番危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の物理化学とは何かについて解説した後、物理化学は難しいのか?や問題を解くためのポイントなどについて解説します。
危険物乙4を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
目次
危険物乙4の物理化学とは?
危険物乙4はガソリンや灯油・軽油・アルコール類など、私たちの生活に身近な危険物を安全に取り扱うための国家資格です。
※「危険物乙4は国家資格で履歴書に書ける!書き方・正式名称は?」もぜひ合わせてご覧ください。
危険物乙4では以下の3分野から問題が出題されます。試験時間は2時間です。
| 分野 | 問題数 |
|---|---|
| 危険物に関する法令 | 15問 |
| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 10問 |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 |
※「危険物乙4の試験時間は2時間で問題数は35問!試験は何時から開始?途中退出も可能!」もぜひ合わせてご覧ください。
「基礎的な物理学及び基礎的な化学(物理化学)」では危険物を取り扱う上で必要な物理・化学の知識を問う問題が出題されます。
具体的には以下の例題のように、中学・高校で学習した物理・化学の基礎知識が出題されます。
【例題】
水に関する記述のうち、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
- 水の三態とは、水蒸気・水・氷の状態をいう。
- 100℃の水が水蒸気になるとき、1gにつき2256.3Jの気化熱を奪う。
- 水が消火に使われる理由の一つには、気化熱の大きいことが挙げられる。
- 水はどんな場合でも100℃で沸騰し、0℃凍る。
- 水1gの温度を14.5℃から15.5℃に高めるのに必要な熱量は、4.186Jである。
【解答&解説】
正解は4・・・(答)です。
水が100℃で沸騰し、0℃凍るのは1気圧のもとです。
気圧が下がれば沸点も下がり、気圧が上がれば沸点は上がります。
危険物乙4の物理・化学で問われる知識は危険物の安全な貯蔵・取扱・運搬を行う上で必要不可欠です。
物理・化学に限らずですが、危険物乙4の知識は実務においても事故を未然に防ぎ、安全を確保するために重要な役割を果たします。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
危険物乙4:物理化学の試験範囲
危険物乙4の物理化学の試験範囲は以下の通りです。
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 物質の状態変化 | 温度と圧力、物質の状態変化、沸騰と沸点、潮解と風解、溶解 |
| 水の性質 | 水の体積と密度、水と二酸化炭素、水の比熱と蒸発熱、水の表面張力と界面活性剤、水溶液の性質 |
| 密度と比重 | 密度、比重、比重と第4類の危険物 |
| 気体の性質 | ボイルの法則、シャルルの法則、ボイル・シャルルの法則 |
| 熱 | 熱容量と比熱、熱の移動、熱膨張 |
| 静電気 | 静電気の発生、静電気の発生のしやすさとその防止方法 |
| 物理変化と化学変化 | 物理変化、化学変化とその種類、物理変化と化学変化の例 |
| 物質の種類 | 純物質と混合物、単体と化合物 |
| 元素・原子・分子 | 元素、原子と分子、原子量と分子量、物質量(モル) |
| 化学反応式・熱化学方程式 | 化学反応式、熱化学方程式 |
| 反応速度・化学平衡 | 反応速度、化学平衡 |
| 酸と塩基 | イオン、酸と塩基、中和・塩、水素イオン指数、リトマス紙 |
| 酸化と還元 | 酸化と還元、酸化剤と還元剤 |
| 金属 | 金属と非金属、金属のイオン化傾向、金属の腐食 |
| 有機化合物 | 有機化合物の性質、有機化合物の官能基による分類 |
| 燃焼の基礎理論 | 燃焼、燃焼の四要素、可燃物、酸素供給体、点火源(熱源) |
| 燃焼のしかた | 完全燃焼と不完全燃焼、燃焼の種類 |
| 燃焼の難易 | 燃焼のしやすさ、燃焼のしにくさ・燃焼の難易に関係しないもの |
| 危険物の性質 | 燃焼範囲と引火点、燃焼点と発火点、自然発火、粉塵爆発 |
| 消火方法 | 消火の四要素、除去消火法、窒素消火法、冷却消火法、抑制消火法 |
| 火災の種類・消火器 | 火災の区分、消火器の表示、消火器の種類、泡消火器と二酸化炭素消火器の特徴、油火災に不適切な消火器 |
以上の試験範囲から必ずといっていいほど出題されるのは静電気と燃焼です。
それぞれの例題は以下の通りです。
【静電気の例題】
静電気に関する説明として、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
- 電気の不良導体を摩擦等すると静電気が発生する。
- 流体がホース内を流れるときに発生する静電気の量は、流速に比例する。
- 静電気は、湿度が低いほど発生しやすく、蓄積しやすい。
- 導電性が高い物質は、導電性が低い物質より静電気を発生しやすい。
- 静電気は、帯電量が多くなると放電火花を発することがある。
【解答&解説】
正解は4・・・(答)です。
導電性が高い物質は、導電性が低い物質より静電気を発生・蓄積しにくい。
【燃焼の例題】
液体の燃焼に直接関係ないものはどれか。1つ選びなさい。
- 沸点
- 引火点
- 発火点
- 燃焼範囲
- 比重
【解答&解説】
正解は5・・・(答)です。
比重は直接的には燃焼には関わりがありません。ただし、消火方法や保存の仕方などには関わりがあります。

危険物乙4の物理化学は難しい?難しいと感じるポイントは?
危険物乙4の物理化学は多くの受験者が苦手意識を持つ科目です。
物理化学では計算問題や化学式・公式に関する問題が出題されるため、難しいと感じる人が多いです。
しかし、危険物乙4の合格ラインを超えるためには物理化学の対策は必須です。
※危険物乙4の合格ラインについて詳しく知りたい人は「危険物乙4の合格点・合格ライン・合格基準が一目でわかる!出題される問題例と合わせて解説!」をご覧ください。
危険物乙4の物理化学で多くの人が難しいと感じるポイントとしては以下の4つがあげられます。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 計算問題 | 危険物乙4ではモル計算、燃焼計算、比重・密度・蒸気密度の計算など様々な計算問題が出題されます。公式を覚えるだけでなく、公式を適切に使いこなす練習が必要です。 |
| 化学式・公式の暗記 | 燃焼範囲、引火点、発火点など様々な数値を覚える必要があります。語呂合わせを利用するなど、自分に合った暗記方法を見つけることが重要です。 |
| 単位の理解 | 危険物乙4では圧力の単位(Pa、kPa、atm)、温度の単位(℃、K)など様々な単位が登場します。単位換算に慣れていないと、計算ミスにつながる可能性があるのでご注意ください。 |
| 用語の定義 | 蒸気圧、飽和蒸気圧、沸点など物理化学特有の用語を正確に理解する必要があります。用語の定義を曖昧にしていると、問題の意味を正しく理解できない可能性があるのでご注意ください。 |
また、危険物乙4では物理化学の知識と他の2科目(「危険物に関する法令」「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」)の知識を関連させた以下のような問題も出題されます。
※「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」もぜひ合わせてご覧ください。
【例題】
第4類危険物の火災に最も多く用いられる消火方法はどれか。正しいものを1つ選びなさい。
- 熱源を除去する方法。
- 可燃性液体と空気との接触を遮断する方法。
- 可燃性蒸気を除去する方法。
- 可燃性液体の温度を引火点未満に下げる方法。
- 可燃性液体を化学的に分解する方法。
【解答&解説】
正解は2・・・(答)です。
第4類危険物の消火は、窒息消火が原則です。
なので、危険物乙4を受験する人は物理化学だけでなく他の2科目(「危険物に関する法令」「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」)もしっかりと学習しておく必要があります。
物理化学は特に以下の分野との関連性が高いです。
<危険物の性質>
引火点・発火点・燃焼範囲などは危険物の性質を理解する上で重要な物理化学の知識です。
<消火方法>
燃焼のメカニズムや消火剤の作用機序を理解するためには物理化学の知識が不可欠です。
<法令>
危険物に関する法令では、物理化学的な数値が基準として用いられています。例としては危険物の分類や貯蔵・取扱いの基準などがあげられます。
危険物乙4では各科目を独立して学習するのではなく、関連性を意識しながら学習することでより効果的に知識を定着させることができます。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
危険物乙4:物理化学で覚えておくべき知識まとめ
ここからは危険物乙4の物理化学で覚えておくべき知識を分野別にご紹介していきます。
物質の状態変化
・固体が直接気体になったり、気体が直接固体になったりする変化は、どちらも昇華。
・沸点は、液体の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる液温のこと。
・外圧が高くなれば沸点も高くなり、外圧が低くなれば沸点も低くなる。
・潮解は水分を吸収して溶けること、風解は水分を失って粉末になること。
水の性質
・水は1気圧4℃のとき、密度は最大になる。
・水の蒸発熱は、他の液体に比べ特に大きく消火(冷却効果)に使われる。
・界面活性剤は、液体の表面張力を小さくする。
・水に不揮発性物質を溶かすと、水の沸点は上昇し、凝固点は下降する。
密度と比重
・密度と比重は同じ数値を示すが、密度には単位があり、比重には単位がない。
・体積が増えると密度は小さくなる。
・物質の蒸気比重の大きさは分子量で比較できる。
気体の性質
・ボイルの法則は、温度と質量が一定の場合、気体の体積は圧力に反比例すること。
・シャルルの法則は、圧力と質量が一定の場合、気体の体積は温度に比例すること。
・ボイル・シャルルの法則は、気体の体積は圧力に反比例し、温度に比例すること。
※上記3つの法則については後ほど詳しく解説します。
熱
・比熱とは、物質1gの温度を1℃上げるのに必要な熱量のこと。
・対流現象は、液体と気体に起こる現象。
静電気
・静電気の一般的な発生メカニズムは、2つ以上の物質の接触、はく離である。
・静電気は、配管内を流れる物質の速度が速いほど発生しやすい。
・静電気は、絶縁性が高いほど、湿度が低いほど帯電しやすい。
・帯電防止策として、流速を遅くする、接地する、湿度を高くする方法などがある。
物理変化と化学変化
・ドライアイスが二酸化炭素になるのは物理変化。
・鉄が錆びてボロボロになるのは化学変化。
物質の種類
・混合物とは、空気やガソリンのように、2種類以上の純物質(単体や化合物)が混じり合った物質のこと。
・単体とは、1種類の元素からなる純物質のことで、それ以上分解できない。
・化合物と混合物の違い=化合物は化学式が書けるが、混合物は化学式が書けない。
・同素体とは、黄リンと赤リンのように、1種類の元素からなる単体で、性質などの異なる物質のこと。
元素・原子・分子
・分子量は、分子に含まれる元素の原子量の総和である。
・1molあたりの質量は、原子量・分子量の値にgをつけたものである。
化学反応式・熱化学方程式
・化学反応式からは、反応物質と生成物の質量や体積がわかる。
・反応熱とは、1molの反応物質が化学変化に伴い、発生または吸収する熱量のこと。
・熱化学方程式は、左辺と右辺を「=」で結び、熱の出入りを「+」または「-」で加える。
・熱化学方程式では、発熱反応は「+」で示し、吸熱反応は「-」で示す。
反応速度・化学平衡
・濃度、圧力、湿度を高くすると反応は速くなる。
・触媒は反応を速くするが、自らは変化しない。
・濃度、圧力、温度を変えると、その変化による影響を緩和する方向に平衡が移動する。
酸と塩基
・酸とは、水に溶けると水素イオン(H+)を生じる物質、または他の物質に水素イオンを与える物質のこと。
・塩基とは、水に溶けると水酸化物イオン(OH–)を生じる物質、または他の物質から水素イオンを受け取る物質のこと。
・pH7であれば中性、pH7より小さければ酸性、pH7より大きければ塩基性。
酸化と還元
・酸化とは、酸素と化合したり、水素を奪われたり、電子を失ったりすること。
・還元とは、酸素を奪われたり、水素と化合したり、電子を受け取ったりすること。
・酸化と還元は同時に起こる。
金属
・金属には燃えるものと燃えないものがある。
・鉄よりイオンか傾向の大きい金属は、マグネシウム、アルミニウム、亜鉛である。
・金属の腐食を防ぐには、配管が鉄の場合は鉄よりイオン化傾向の大きい金属と接続する、強塩基性のコンクリートの中に埋没するなどがある。
有機化合物
・有機化合物が完全燃焼すると、二酸化炭素と水を生成する。
・有機化合物は一般に、融点や沸点が低く、反応速度が遅く、反応機構は複雑である。
・有機化合物の官能基の主なものには、水酸基、アルデヒド基、ケトン基、カルボキシル基がある。
燃焼の基礎理論
・燃焼とは、熱と光の発生を伴う酸化反応のこと。
・燃焼の三要素とは、可燃物、酸素供給体、点火源。3つがそろわなければ燃焼は起こらない。
・酸素供給体になるものは、空気、第1類・第6類の危険物。
・点火源になるものは、炎・熱のほかに、静電気火花、酸化熱など。
燃焼のしかた
・完全燃焼では二酸化炭素、不完全燃焼では一酸化炭素が生じる。
・第4類の危険物の燃焼はすべて蒸発燃焼。
・固体の表面燃焼は、表面で直接酸素と反応して燃焼する。
・固体の分解燃焼は、加熱で分解されて発生する可燃性気体が燃焼する。
・固体の自己燃焼は、分子内に酸素を含み、分解して燃焼する。
・蒸発燃焼は、液体や固体から気体になって燃焼する。
燃焼の難易
・発熱量が大きいほど、燃焼しやすい。
・熱伝導率が小さい物質ほど、燃焼しやすい。
・空気との接触面が大きいほど、燃焼しやすい。
・水分が少ない、つまり、乾燥しているほど燃焼しやすい。
・温度が高いほど、燃焼しやすい。
危険物の性質
・燃焼範囲とは、点火により燃焼する可燃性気体と空気の混合気体の濃度の範囲。
・引火点とは、燃え出すのに十分な蒸気を発生するときの最低の液温(点火源あり)
・発火点とは、加熱により、点火源なしに自ら発火して燃焼を開始する最低の温度。
・引火点<燃焼点<発火点の順に高くなる。
・自然発火とは、物質が空気中で発熱した熱が蓄積されて発火点に達し燃焼すること。
・自然発火の発熱原因には、分解熱や酸化熱、吸着熱などがある。
消火方法
・燃焼の三要素のうち、どれか1つを取り除けば消火できる。
・除去消火法は、可燃物を取り除く方法。例:ろうそくの火を吹き消す。
・窒息消火法は、酸素を遮断する方法。例:アルコールランプの炎にふたをする。
・冷却消火法は、燃焼物の温度を下げて熱源となる熱を奪う方法。
・抑制消火法は、燃焼の連鎖反応を抑制する方法。
火災の種類・消火器
・冷却効果のある消火器:水、強化液、泡、二酸化炭素。
・窒息効果のある消火器:泡、二酸化炭素、ハロゲン化物、粉末。
・抑制効果:霧状の強化液、ハロゲン化物、粉末。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
危険物乙4:物理化学の重要公式・覚え方は?計算問題付き
危険物乙4の物理化学では計算問題が出題されます。
計算問題を解くためには公式の暗記が必須です。
ここからは、物理化学の計算問題を解くために必要な公式と覚え方・計算問題をご紹介していきます。
※「危険物乙4の計算問題で必要な公式まとめと過去問に似た例題!難しい?捨てるのはあり?」もぜひ合わせてご覧ください。
温度
絶対温度=セ氏温度+273
※セ氏温度は日常生活で使われる温度で、1気圧下での氷の融解点を0℃、水の沸点を100℃としてその間を100等分したものです。単位は℃で表します。
※絶対温度はシャルルの法則(後ほどご紹介)で、気体の体積が0になる温度(-273℃)を絶対零度とする尺度です。論理的にこれより低い温度は存在しません。単位はK(ケルビン)を表します。
ボイルの法則
温度と湿度が一定の状態で、圧力P1、体積V1の気体を圧力P2、体積V2にした場合、以下の関係式が成り立ちます。
P1 × V1 = P2 × V2
【計算問題】
2気圧で24Lの理想気体を容器に入れたところ、内部の圧力が6気圧となった。この容器の容積として、次のうち正しいものはどれか。ただし、理想気体の温度は変化しないものとする。
- 6L
- 8L
- 12L
- 48L
- 72L
【解答&解説】
正解は2・・・(答)です。
ボイルの法則を使います。求める容器の容積をVとすると、2 × 24=6 × Vより、V=8[L]となります。
シャルルの法則
圧力と質量が一定の状態で、絶対温度T1、体積V1の気体を絶対温度T2、体積V2にした場合、以下の関係式が成り立ちます。ただし、シャルルの法則で示す温度は絶対温度です。
V2 = V1 × T2/T1
ボイル・シャルルの法則
ボイルの法則とシャルルの法則をまとめてボイル・シャルルの法則といいます。
絶対温度T1、圧力P1、体積V1の気体を、絶対温度T2、圧力P2、体積V2にした場合、以下の関係式が成り立ちます。
(P1 × V1)/ T1 = (P2 × V2)/ T2
熱容量
質量m[g]の物質の比熱をc[J/(g・℃)]とすると、熱容量C[J/℃]は以下の式で表すことができます。
C=c × m[J/℃]
熱量
質量m[g]の物質の温度がt1[℃]からt2[℃]に変化した場合、この物質に出入りする熱量Q[J]を求める式は以下のようになります。
Q=C × (t2 – t1)=c × m ×(t2 – t1)[J]
【計算問題】
0℃で100gの物質に12.6kJの熱量を加えると、物質の温度は何℃になるか。ただし、物質の比熱を2.1J/(g・℃)とする。
- 50℃
- 60℃
- 70℃
- 80℃
- 90℃
【解答&解説】
正解は2・・・(答)です。
上昇後の温度をt2[℃]とすると、以下の式が成り立ちます。
12,600=2.1 × 100 ×(t2 – 0)
よって、t2=12,600 ÷ 210=60[℃]となります。
膨張後の体積
温度上昇に伴い、固体や液体の体積がどれくらい膨張するかは以下の式で表します。
※元の体積をV0、体膨張率をα[K-1]とし、温度がt[℃またはK]上昇したときの体積をVとします。
V=V0 × (1+α×t)
容量パーセント
燃焼範囲は、可燃性気体と空気の混合気体全体に対する可燃性気体の割合を容量パーセント[vol%]で表します。
容量パーセント[vol%]=可燃性気体[L] / (可燃性気体[L]+空気[L]) × 100
【計算問題】
次の性質を持つ引火性液体が燃焼しない状態はどれか。
引火点-40℃、発火点約300℃、燃焼範囲1.4〜7.6vol%
- 蒸気4L、空気96Lの混合気体に点火した。
- 液温-20℃のときに炎を近づけた。
- 400℃の高温体に接触させた。
- 100℃まで加熱した。
- 蒸気を7L含む空気200Lに点火した。
【解答&解説】
正解は4・・・(答)です。
選択肢を順番に見ていきます。
1:可燃性蒸気4L、空気96Lの混合気体中の可燃性蒸気の容量パーセントは、4/(4+96) × 100=4/100 × 100=4[vol%]となり、燃焼範囲であることがわかります。
燃焼範囲の場合、点火すれば燃焼します。
2:点火源を近づけた場合、燃焼する最低の液温が引火点です。引火点が-40℃ならば、それ以上の液温-20℃のとき炎を近づけると燃焼します。
3:400℃の高温体を接触させると引火性液体も400℃まで加熱され、発火点約300℃を超えるため、点火源がなくても燃焼します。
4:この選択肢には点火源の有無の記載がありません。100℃は引火点を超えていますが、点火源がなければ燃焼しません。また、点火源がなくても加熱によって燃焼しはじめる液温は発火点です。この引火性液体の発火点は約300℃なので、約300℃まで加熱しなければ燃焼はしません。
5:選択肢1と同様に計算します。可燃性蒸気の容量パーセントは7/200 × 100=3.5[vol%]となり、燃焼範囲内なので燃焼します。
ちなみに、この引火性液体は第4類・第1石油類のガソリンです。
危険物乙4:物理化学の勉強のポイント
物理化学の学習を効果的に進めるためのポイントは以下の3つです。
- 用語をしっかりと暗記する
- 危険物の性質との関係を理解する
- 公式を暗記し、単位をそろえて計算する
それぞれの詳細は以下です。
1:用語をしっかりと暗記する
物理化学に限らずですが、危険物乙4では暗記しなければならない用語がたくさん登場します。
なので、まずは用語の暗記を確実に行いましょう。用語の暗記は参考書を購入して行うことをおすすめします。
※「危険物乙4のおすすめテキスト・参考書・問題集ランキング2025!人気なのはどれ?」もぜひ合わせてご覧ください。
現在は本屋やAmazonなどで数多くの参考書が販売されていますが、筆者がおすすめする参考書はユーキャンから出版されている『ユーキャンの乙種第4類危険物取扱者 速習レッスン』です。
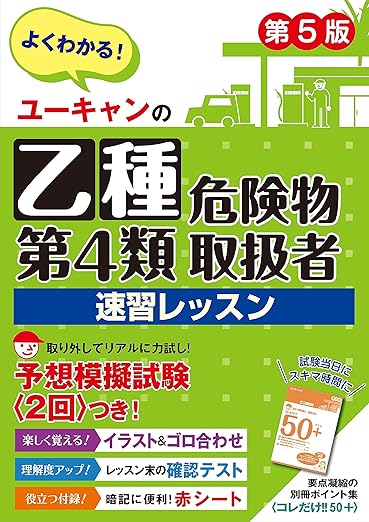
乙子先生とシロー君の掛け合いが楽しい1コママンガや自然と暗記が進むゴロ合わせなどが用意されているため、勉強が苦手な人でもスムーズに学習を進めることができます。
また、各レッスン末には学んだ知識が定着しているかを確認できる丸バツテストも用意されています。
模擬試験も2回分掲載されているので、危険物乙4を受験予定の人はぜひ購入を検討してみてください。
※「危険物乙4の模擬試験が無料!丁寧な解答・解説付き!」もぜひ合わせてご覧ください。
2:危険物の性質との関係を理解する
上記でも解説した通り、危険物乙4では物理化学の知識と他の2科目(「危険物に関する法令」「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」)の知識を関連させた問題も出題されます。
その中でも物理化学は特に、危険物の性質を十分に理解した上で学習すると、より効率的に知識を深められます。
危険物の性質については「危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせで紹介!性質の問題例は?」で詳しく解説しているので、物理化学を学習する前に必ずチェックしておきましょう。
3:公式を暗記し、単位をそろえて計算する
上記でご紹介した物理化学の公式を暗記したら、計算問題の演習を積んでいきましょう。
計算問題では単位をそろえて計算することを意識してください。
特に熱量に関する問題ではkJ⇔Jの変換が必要なケースが多いのでご注意ください。
例題は以下です。
【例題】
比熱が2.5J/(g・K)の液体100gの温度を10℃から30℃まで上昇させるために必要な熱量は何kJか。
【解答&解説】
まずは℃をKに変換します。
10℃=10+273=283[K]、30℃=30+273=303[K]です。
2.5[J/(g・K)]× 100[g] ×(303-283)[K]
=2.5 × 100 × 20
=5,000[J]
=5[kJ]・・・(答)となります。
※1,000J=1kJです。
危険物乙4:物理化学の過去問は入手できる?過去問の例題は?
危険物乙4の過去問は一般財団法人消防試験研究センターのホームページに掲載されています。
しかし、掲載されているのは問題のみです。解答と解説は掲載されていないのでご注意ください。
解答・解説付きの過去問を解きたい人は『乙種4類 危険物取扱者試験』を購入しましょう。料金は税込1,870円です。
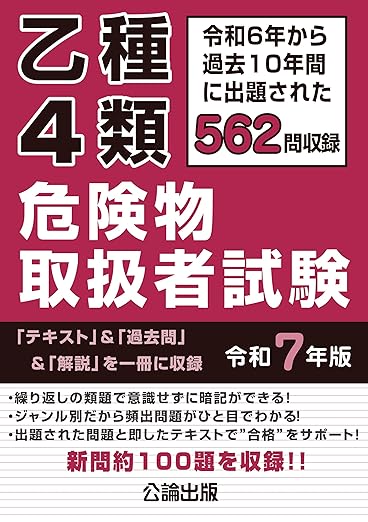
『乙種4類 危険物取扱者試験』には令和6年から過去10年間に出題された過去問562問が収録されています。
危険物乙4では過去問の類似問題が数多く出題されるので、危険物乙4を受験予定の人は必ず購入しておくことをおすすめします。
本記事では危険物乙4の過去問を科目別に1問ずつご紹介します。
解答&解説付きなので、ぜひ解いてみてください。
※「危険物乙4の過去問・試験問題100問が無料!解説付き!PDFも配布!」もぜひ合わせてご覧ください。
【危険物に関する法令の過去問】
予防規程について、正しいものを1つ選びなさい。
- 予防規程を定めたときは、市町村長等に届け出なければならない。
- 予防規程を定めたときは、市町村長等の承認を受けなければならない。
- 予防規程を定めたときは、市町村長等の許可を受けなければならない。
- 予防規程を変更したときは、市町村長等の認可を受けなければならない。
- 予防規程を変更したときは、市町村長等に届け出なければならない。
【解答&解説】
正解は4・・・(答)です。
消防法第14条の2に「予防規程を定め、市町村長等の許可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする」とされています。
承認や許可ではないことに注意しましょう。
【基礎的な物理学及び基礎的な化学の過去問】
次の物質のうち、可燃物ではないものはどれか。1つ選びなさい。
- 一酸化炭素
- 窒素
- 硫化水素
- 硫黄
- 炭素
【解答&解説】
正解は2・・・(答)です。
窒素は不燃物です。
【危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法の過去問】
第4類危険物の消火方法として、適当でないものはどれか。1つ選びなさい。
- ガソリンの火災に、粉末(ABC)消火器を用いる。
- 軽油の火災に、二酸化炭素消火器を用いる。
- 重油の火災に、棒状の強化消火器を用いる。
- あまに油の火災に、化学泡消火器を用いる。
- ギヤー油の火災に、ハロゲン1211消火器を用いる。
【解答&解説】
正解は3・・・(答)です。
重油の火災に適するのは、泡・粉末・二酸化炭素などの消火剤です。
第4類危険物の一般的な火災に水はもちろん不適合ですが、強化液消火剤を使用する場合も棒状のものではなく、霧状の強化液を用います。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
今回は危険物乙4の物理化学について詳しく解説していきました。
物理化学では計算問題も出題されるので難しいと感じる人も多いですが、公式がしっかりと頭に入っていればそこまで難しくはありませんのでご安心ください。


