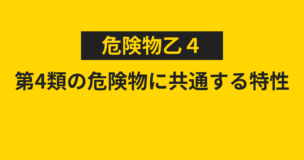
本記事では第4類の危険物に共通する特性について詳しく解説していきます。
特に火災予防方法は本番の試験でも頻出なので、危険物乙4を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
目次
第4類の危険物に共通する性質
第4類の危険物に共通する特性を覚えてしまえば、個々の危険物について覚えることは格段に少なくなります。
共通する特性とは以下の3つを指します。
- 共通する性質
- 共通する火災予防方法
- 共通する消火方法
第4類の危険物は引火性の液体です。
第4類の危険物の特徴は、液体の表面から発生する可燃性蒸気に引火して燃焼する危険性があることです。
可燃性蒸気は、液温が高くなるほど発生量が多くなります。
第4類の危険物は、
- 引火点や沸点、発火点が低いもの
- 燃焼範囲が広く燃焼下限値が低いもの
ほど、危険性が高くなります。
引火点や沸点、発火点に関する問題が出題された場合は以下のの2つを思い出すと、1つ1つの危険物の数値を覚えていなくても正解がわかることがあります。
1:消防法における第4類の危険物の品名は、危険性の高い順に並んでいる。
特殊引火物→第1石油類→アルコール類→第2石油類→第3石油類→第4石油類→動植物油類
2:消防法では、第4類の危険物の品名は、引火点や沸点、発火点の数値によって定義されているものが多い。
第4類の危険物に共通する性質
第4類の危険物に共通する性質は以下の通りです。
1:いずれも引火性の液体で、可燃性の気体(蒸気)を発生する。
2:比重は1より小さい(水より軽い)ものが多い。
3:いずれも蒸気比重は1より大きい(空気より重い)。
4:蒸気は低所に滞留して遠くに流れる。
5:ほとんどが発火点100℃以上である。
6:水に溶けない(非水溶性)ものが多い。
7:発生した蒸気は、空気と混合物をつくり、火気などにより引火または爆発の危険性がある、
8:霧状になったものは、空気との接触面が大きくなり、危険性が増す。
9:電気の不導体(不良導体ともいう)で静電気を蓄積しやすく、蓄積された静電気が放電し、発生した火花によって引火する危険性がある。水溶性のものより非水溶性のもののほうが、静電気を蓄積しやすい。
10:流動性があるため、流出した場合、水の表面に薄く広がって液表面積が大きくなる。火災が発生した場合には、延焼など拡大する危険性がある。
11:過酸化水素や硝酸のような酸化剤などと混合すると、発火の危険性がある。
水より重い第4類の危険物
第4類の多くは水より軽い危険物ですが、比重が1より大きい(水より重い)危険物もあります。
第4類のうち、水より重い主な危険物は以下の表の通りです。
| 品名 | 危険物 | 比重 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 二硫化炭素 | 1.26 |
| 第2石油類 | クロロベンゼン | 1.1 |
| 酢酸 | 1.05 | |
| アクリル酸 | 1.05 | |
| 第3石油類 | アニリン | 1.01 |
| ニトロベンゼン | 1.2 | |
| エチレングリコール | 1.1 | |
| グリセリン | 1.26 |
水溶性の第4類の危険物
第4類の多くは水に溶けない(非水溶性)危険物ですが、水に溶ける(水溶性)危険物もあります。
第4類のうち、主な水溶性液体は以下の表の通りです。
| 品名 | 危険物 |
|---|---|
| 特殊引火物 | アセトアルデヒド |
| 酸化プロピレン | |
| 第1石油類 | アセトン |
| ピリジン | |
| ジエチルアミン | |
| すべてのアルコール類 | |
| 第2石油類 | 酢酸 |
| プロピオン酸 | |
| アクリル酸 | |
| 第3石油類 | エチレングリコール |
| グリセリン | |
非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものをいい、水に溶けにくい(難溶)ものや、水にわずかに溶ける(少溶)ものも非水溶性に含まれます。
水溶性液体とは、1気圧20℃(常温)において同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまったあとも混合液が均一な外観を維持するものをいいます。
また、第4類の水溶性液体には、一般の泡消火剤では効果がないため、水溶性液体用泡消火剤を使用して消火します。
※水溶性液体用泡消火剤は耐アルコール泡消火剤とも呼ばれます。
第4類の危険物の液体色
第4類の危険物はほとんどが無色の液体ですが、中には色がついた危険物もあります。
第4類のうち、無色ではない危険物は以下の表の通りです。
| 品名 | 危険物 | 液体色 |
|---|---|---|
| 第1石油類 | 自動車ガソリン | オレンジ色(着色) |
| 第2石油類 | 灯油 | 無色またはやや黄色 |
| 軽油 | 淡黄色または淡褐色 | |
| 第3石油類 | 重油 | 褐色または暗褐色 |
| クレオソート油 | 黄色または暗緑色 | |
| アニリン | 無色または淡黄色 | |
| ニトロベンゼン | 淡黄色または暗黄色 |
第4類の危険物に共通する火災予防方法
第4類の危険物に共通する火災予防方法は以下の通りです。
1:炎や火花、発火の原因となる高温体との接近を避ける。
2:加熱を避ける。
3:容器は、密栓して冷暗所に貯蔵する。
4:容器を密栓する場合は、危険物の体膨張による漏れなどが生じないよう、容器中に空間をとる。
5:みだりに蒸気を発生させない。
6:十分な通風や換気を行う。
7:低所に滞留した蒸気は、屋外の高所に排出する。
8:蒸気が滞留するおそれのある場所では、火花を発生する機械器具などは使用しない。
9:著しく蒸気が滞留するおそれがある場所の電気設備は、防爆構造のものを使う。
10:危険物の流動などにより静電気が発生するおそれがある場合は、接地(アース)などにより有効に静電気を除去する。
11:かくはんや注入は、流速を下げて(ゆっくり)行い、静電気の発生を抑制する。
12:作業着などは、合成繊維のものの着用を避け、帯電防止加工をしたものを着用する。
13:酸化剤などと接触させない。
14:川や下水溝に流出させない。
この他に、二硫化炭素は可燃性蒸気の発生を防ぐため、水を張った容器や水没させたタンクなどで貯蔵します。
第4類の危険物に共通する消火方法
第4類の危険物は可燃物の除去による消火(除去消火)や注水による冷却消火ができません。
第4類の危険物の火災の消火には、油火災に有効な、空気を遮断する窒息効果や燃焼の連鎖反応を抑制する抑制効果のある消火剤を使用します。
第4類の危険物の火災に有効な消火剤と、その消火効果は以下の通りです。
●霧状の強化液消火剤=抑制効果
●二酸化炭素消火剤=窒息効果
●泡消火剤=窒息効果
●粉末消火剤=窒息効果、抑制効果
●ハロゲン化物消火剤=窒息効果、抑制効果(負触媒効果)
●乾燥砂=小規模火災ならば窒息効果を利用して有効
第4類の危険物に適応しない消火方法
第4類の危険物火災には、危険性があるため使用できない消火剤があります。
具体的には以下です。
●棒状の強化液消火剤は、流動性を持つ第4類の危険物に放射すると、被害が拡大するおそれがあるため使用できない。
●比重が1より小さい危険物に注水すると、危険物が水に浮いて流出し、火災範囲を広げてしまうため、水による消火はできない。
水溶性液体の消火方法
アルコール類などの水溶性液体の火災に泡消火剤を使用すると、一般の泡消火剤の泡の水膜を溶かして(泡が消えて)しまい、窒息効果が得られません。
泡消火剤は、泡が溶解したり破壊されたりしない水溶性液体用泡消火剤(耐アルコール泡消火剤)を使用します。
以上
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽


